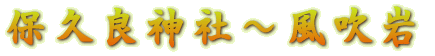
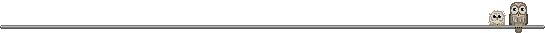
2005年11月15日(火) 晴れ
2005年秋紅葉、近場散策第2回。地元阪神間の裏山、六甲山東側を少し歩こうと、東おたふく山から岡本へ下りる予定で、阪急芦屋川駅北側の芦有バス停留所へ行ったら、1時間に1本しかないバスが行ったばかり。1時間近く待つなんていやだし、もう1駅西へ、岡本まで電車で行き、登りを歩いて帰りにバスを使おうと、今降りたばかりの電車にまた乗った。
 岡本駅から住宅街を抜けて、金鳥山の中腹にある保久良神社までは、コンクリートの急坂で、あまり歩きたくない道だけど50分で登れるはずだった。だけどサクラの紅葉のきれいな落ち葉をあちこちで拾ったりして、1時間半後にやっと到着。何年ぶりかなぁ。1995年の阪神淡路大震災で鳥居、本殿、玉垣石柱など無残に崩壊していたのが、鳥居は翌年、本殿はそれからしばらくして改修中だった頃来たきり。今回はすっかり修復されていた。 岡本駅から住宅街を抜けて、金鳥山の中腹にある保久良神社までは、コンクリートの急坂で、あまり歩きたくない道だけど50分で登れるはずだった。だけどサクラの紅葉のきれいな落ち葉をあちこちで拾ったりして、1時間半後にやっと到着。何年ぶりかなぁ。1995年の阪神淡路大震災で鳥居、本殿、玉垣石柱など無残に崩壊していたのが、鳥居は翌年、本殿はそれからしばらくして改修中だった頃来たきり。今回はすっかり修復されていた。
 この神社は、大昔の火事か何かで記録がなくなっていて起源ははっきりしないが、随分古くからあったらしい。境内にごろごろあった巨石そのものも信仰の対象だったそうだが、今はしめ縄を掛けられたひとつしか目にしない。地元では早朝登山などで親しまれている。 この神社は、大昔の火事か何かで記録がなくなっていて起源ははっきりしないが、随分古くからあったらしい。境内にごろごろあった巨石そのものも信仰の対象だったそうだが、今はしめ縄を掛けられたひとつしか目にしない。地元では早朝登山などで親しまれている。
 鳥居の前に、何の変哲もないような石灯篭がひとつ建っている。“灘の一ツ火”と呼ばれているそうだ。 鳥居の前に、何の変哲もないような石灯篭がひとつ建っている。“灘の一ツ火”と呼ばれているそうだ。
 |
 |
上記案内板をクリックすると
拡大画像が別窓で開きます |
そばの石碑に曰く、『この石灯籠は、文政八年(1825年)のものですが、往古は、“かがり火”を燃やし、 中世の昔より“油”で千古不滅の御神火を点じつづけ、最初の灯台として「灘の一ツ火」と海上の船人の目じるしにされました。古くから、ふもとの北畑村の天王講の人々が、海上平安を願う「祖神」の遺志を継承し、交替で点灯を守りつづけてきたものです。』 今は、電灯がつくそうだ。

岡本からの登山道は、急なコンクリート坂だったり、石段だったり
足にはちょっとつらいけど、神戸の街を見下ろすこんな景色が随所で見られて
しんどいことをしばし忘れさせてくれる
 |
 |
 |
| 最初は石段や木の階段ばかり |
六甲山東側に多い掘られたような道 |
やっと風吹岩の北側に到着 |
ほとんど花崗岩でできている六甲山は崩れやすく、左の石段にしたり、
平らなところは獣道から雨の道、人の道と広がってこうなったのではないか |
|
 岡本駅から住宅街を抜けて、金鳥山の中腹にある保久良神社までは、コンクリートの急坂で、あまり歩きたくない道だけど50分で登れるはずだった。だけどサクラの紅葉のきれいな落ち葉をあちこちで拾ったりして、1時間半後にやっと到着。何年ぶりかなぁ。1995年の阪神淡路大震災で鳥居、本殿、玉垣石柱など無残に崩壊していたのが、鳥居は翌年、本殿はそれからしばらくして改修中だった頃来たきり。今回はすっかり修復されていた。
岡本駅から住宅街を抜けて、金鳥山の中腹にある保久良神社までは、コンクリートの急坂で、あまり歩きたくない道だけど50分で登れるはずだった。だけどサクラの紅葉のきれいな落ち葉をあちこちで拾ったりして、1時間半後にやっと到着。何年ぶりかなぁ。1995年の阪神淡路大震災で鳥居、本殿、玉垣石柱など無残に崩壊していたのが、鳥居は翌年、本殿はそれからしばらくして改修中だった頃来たきり。今回はすっかり修復されていた。 この神社は、大昔の火事か何かで記録がなくなっていて起源ははっきりしないが、随分古くからあったらしい。境内にごろごろあった巨石そのものも信仰の対象だったそうだが、今はしめ縄を掛けられたひとつしか目にしない。地元では早朝登山などで親しまれている。
この神社は、大昔の火事か何かで記録がなくなっていて起源ははっきりしないが、随分古くからあったらしい。境内にごろごろあった巨石そのものも信仰の対象だったそうだが、今はしめ縄を掛けられたひとつしか目にしない。地元では早朝登山などで親しまれている。 鳥居の前に、何の変哲もないような石灯篭がひとつ建っている。“灘の一ツ火”と呼ばれているそうだ。
鳥居の前に、何の変哲もないような石灯篭がひとつ建っている。“灘の一ツ火”と呼ばれているそうだ。






 見晴らしはいいし自分チも見えるし、汗が引くいい風も吹いていて、とてもいい場所だけど、以前午後遅い頃、といっても2時半ぐらいだけど、ひとりでボーと景色を眺めていたら、下の地獄谷から大きないのししがヌッと上ってきて肝を冷やしたことがあって、 ひとりではちょっとこわい。だけど今日は先客男性がひとり一段高い岩の上でお弁当中。ほとんど同時に男性二人組みが岡本からも芦屋側からも来られて、安心。みなさん眺望を楽しんでおられるので邪魔にならないように、石と潅木の陰でリュックを下ろして、さあ、ランチタイムだとリュックを開けたら、それまで3匹しか見なかった猫が10匹になって、 何と!そんなに大きくはないけれどいのししも目の前の谷から上ってきて、膝のところで食べ物を待っている。いやぁ、そんなにないし、こわいよぉ。がさごそ急いでしまって立ち上がった。
見晴らしはいいし自分チも見えるし、汗が引くいい風も吹いていて、とてもいい場所だけど、以前午後遅い頃、といっても2時半ぐらいだけど、ひとりでボーと景色を眺めていたら、下の地獄谷から大きないのししがヌッと上ってきて肝を冷やしたことがあって、 ひとりではちょっとこわい。だけど今日は先客男性がひとり一段高い岩の上でお弁当中。ほとんど同時に男性二人組みが岡本からも芦屋側からも来られて、安心。みなさん眺望を楽しんでおられるので邪魔にならないように、石と潅木の陰でリュックを下ろして、さあ、ランチタイムだとリュックを開けたら、それまで3匹しか見なかった猫が10匹になって、 何と!そんなに大きくはないけれどいのししも目の前の谷から上ってきて、膝のところで食べ物を待っている。いやぁ、そんなにないし、こわいよぉ。がさごそ急いでしまって立ち上がった。

 お腹すいてるのにぃ。いい景色を見ながらおにぎりを食べるのを楽しみに、がんばって登ってきたのにぃ。といっても、保久良神社からここまで、足が弱ったんだろうなぁ。予定より30分も余計にかかってしまったから、下からでは1時間以上遅くなっている。秋の日はつるべ落とし。特に山の午後は早い。
今日はこの後東おたふく山まで登って、バスで下りるのは諦めた。腹が減っては戦はできぬ。もと来た道を下る。観光施設がいろいろある山頂が見える。ここから見る六甲山頂やその前の谷間の景色が好きだ。
お腹すいてるのにぃ。いい景色を見ながらおにぎりを食べるのを楽しみに、がんばって登ってきたのにぃ。といっても、保久良神社からここまで、足が弱ったんだろうなぁ。予定より30分も余計にかかってしまったから、下からでは1時間以上遅くなっている。秋の日はつるべ落とし。特に山の午後は早い。
今日はこの後東おたふく山まで登って、バスで下りるのは諦めた。腹が減っては戦はできぬ。もと来た道を下る。観光施設がいろいろある山頂が見える。ここから見る六甲山頂やその前の谷間の景色が好きだ。 少し下りたところに小さいベンチを置いてある見晴らしのいいところがあるからそこでおにぎりを。
少し下りたところに小さいベンチを置いてある見晴らしのいいところがあるからそこでおにぎりを。 保久良神社まで下りたところで、30年ぶりに梅林の方へ行ってみる。息子の幼稚園卒園記念クラス会で初めて来たのは花の時期、まだ木々は小さく、幼児が走り回ったところが立派な林になっている。そこで山の上のほうの様子を聞かれた人から逆に教えてもらったもみじ通りを下りることにした。昨年に比べてサクラの紅葉はどこもきれいだけれど、カエデは随分遅れている。
保久良神社まで下りたところで、30年ぶりに梅林の方へ行ってみる。息子の幼稚園卒園記念クラス会で初めて来たのは花の時期、まだ木々は小さく、幼児が走り回ったところが立派な林になっている。そこで山の上のほうの様子を聞かれた人から逆に教えてもらったもみじ通りを下りることにした。昨年に比べてサクラの紅葉はどこもきれいだけれど、カエデは随分遅れている。



