
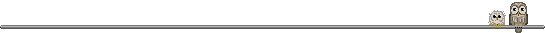
2010年3月11日(木) 晴れ ときどき くもり
昔から梅で有名な京都北野天満宮へ初めて行ってきた。梅の木の本数とか多彩さとかでは、他にいっぱい観梅名所があるけれど、ここは由緒正しさで一番じゃないか。
天神さんは、叡智すぐれた菅原道真にあやかろうと、今は書道、学問の神様として、書初めや受験生の合格祈願絵馬奉納などでよく知られるが、政敵による謀略によって北九州大宰府に左遷された道真の祟りが都に疫病、天変地異を起こしたと恐れられ、怨霊を鎮めるためにこの地に946年天神として祀られたといわれる。
 |
 |
| 楼門手前にある豊臣秀吉が天正15年に催した『北野大茶会』ゆかりの井戸だとか |
 |
 |
楼 門
|
|
三光門 |
 |
三光門に張られた結界を示す注連縄
ちなみに、縄は雲、紙は雷、下がっている穂は雨を示すそうだ |
 |
 |
三光門の名前のもとになったと言われる日光(左)と月光(右)の彫刻
もうひとつは星と言われるが、どこにあるか分からなかった |
天満宮を建てた後に余った材木を使って、近くに7軒の家が建ったそうで、それが京都の花街としては祇園よりも古い上七軒なのだそうだ。今もちゃんと芸者さん舞妓さんのいる花街らしい。そばが西陣の街だから、裕福な旦那衆が多かったということか。今は、少し北になる紫野あたりの表通りに軒を連ねていた多くの古くからの呉服店が11階建てのマンションになっているらしい。
 |
天満宮に祀られている菅原道真と牛は関わりが深いもののようだ
丑年生まれとか、牛に救われたことがあるとか |
 |
 |
| この黒い牛は牡を表し |
こちらの珍しいまだら石の牛は雌を表すらしい
自分の悪いところを撫でるとよくなると言うので
左右の足を撫でさすった |
 楼門を入ったところに大きくて立派な絵馬堂が建っていた。大勢の人で賑わって、中の床机に腰掛けて眺めている人もいる。大きいのや小さいのや随分古そうなのから真新しいのまで重ねて飾ってあるようだ。 楼門を入ったところに大きくて立派な絵馬堂が建っていた。大勢の人で賑わって、中の床机に腰掛けて眺めている人もいる。大きいのや小さいのや随分古そうなのから真新しいのまで重ねて飾ってあるようだ。
今では手のひらサイズの5角形の木片に願い事を書いて奉納するのがどこでも普通だけど、もともとは、本物の馬を奉納したものらしい。本物の馬では奉納される神社のほうも世話が大変だし、奉納するほうもお金がかかるし、馬の彫刻、馬の絵になり、そのうちにいろんな絵柄の絵馬になっていったのだという。
ゆっくり見るのは次の機会にして、今日は梅見。
 |
| みなさん行儀よく2列に並んで参拝順を待つ、これは珍しいのじゃないか |
 |
国宝の拝殿(後ろに本殿があるらしい)はなかなかに色鮮やかな欄間彫刻、真ん中、梅の紋と大鈴の上にはやはり牛
|
 |
 |
| 向かって左に龍、右に虎、他はよく分からないが、干支ではなさそう |
 |
 |
右近の梅
|
|
左近の松 |
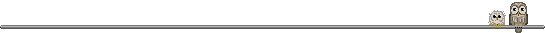
入場券売り場の横からチラッと見てもそれほど広そうにも満開にも見えない梅林だけど、御土居なる昔の土手を歩けるというので入ってみることにした。

御土居という土手の上から下を見る
写真をクリックすると御土居についての案内板が別窓で出ます
 |
 |
| 昆布茶とお菓子を梅林横でよばれたが、目の前の木はほぼ終わっていて、2月末が満開だったか |
 |
 |
| しだれ梅はきれいに咲いて、色合いもほんのり桃色美しい |
 |
 |
| 梅林を出たところにも牛 |
こちらの足元には子牛が |
西陣の名のおこりは、応仁の乱(1467年(応仁1)から11年間続いた内乱)で堀川をはさんで東の陣地と西の陣地がおかれ、東は名前が残っていないが、西に織物関係の職人町ができて西陣の名前が引き継がれたそうだ。その堀川は今は暗渠になって堀川通りの下を流れているらしい。
|











 楼門を入ったところに大きくて立派な絵馬堂が建っていた。大勢の人で賑わって、中の床机に腰掛けて眺めている人もいる。大きいのや小さいのや随分古そうなのから真新しいのまで重ねて飾ってあるようだ。
楼門を入ったところに大きくて立派な絵馬堂が建っていた。大勢の人で賑わって、中の床机に腰掛けて眺めている人もいる。大きいのや小さいのや随分古そうなのから真新しいのまで重ねて飾ってあるようだ。










