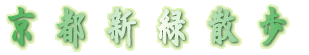

2011年5月9日(月) 晴れ というか うす曇り
親鸞聖人750回忌の今年、大遠忌法要が行われる西本願寺と、紅葉で有名な東福寺と瑠璃光院もこの新緑の時期に特別公開というので、いつものようにバスツアーに参加しました。
 |
 |
九条通りだったか広い道路でバスから下ろされ
東福寺の塔頭が並ぶ路地を歩きます |
入り口に当たる臥雲橋から通天橋を望む
秋には真っ赤に染まる下の渓谷‘洗玉澗’を埋める
カエデの新緑 |
6年前の秋、評判の紅葉を見ようとやって来て、この土塀の辺りで右股関節が痛くて足が進まなくなってしまったのを思い出しました。股関節痛が一段とひどくなったことを自覚させられた東福寺・紅葉狩り。休み休みまわって眺めた紅葉はみごとでしたが、苦い思い出になりました。よろしかったらそのときの様子はこちらをどうぞ。
方丈とは禅宗寺院における僧侶の住居で、後に相見(応接)の間ともなっていったそうです。明治時代に火災にあいましたが9年後に再建され、昭和14年には、作庭家・重森三玲によって方丈の四周にめぐらせた庭が完成。八相の庭と呼ばれる名庭園として名高いそうです。
 |
 |
| 南庭 |
西庭 |
 |
西庭から北庭へ向かう途中に通天台があり
眼下に洗玉澗と、向こうに通天橋と渡り廊下が望めます |
 |
 |
| 北庭 苔と敷石によって市松模様に配された独特の庭 |
東庭 北斗七星に見立てた石と、後方の生垣は
天の川をあらわしているという |
いつもは非公開の国宝龍吟庵が公開されていました。東福寺塔頭の一つで、室町時代初期建築の方丈は、応仁の乱以前の書院造と寝殿造が融合した現存最古の建築物だとか。
太閤秀吉の正室おねがよく訪れたが、渓谷を渡るのに橋がなく不便で、偃月橋(えんげつきょう)が架けられたそうです。東福寺には、臥雲橋、通天橋という渓谷にかかる屋根のある木造橋が他に二つあり、この偃月橋を合わせて三名橋と呼ぶとか。
建物内は撮影禁止です。
 |
 |
| 偃 月 橋 |
 |
 |
南庭、無の庭 白砂を敷き詰めただけ
竹垣は稲妻をあらわしているという |
西庭、龍の庭 白砂と黒砂は雲を
石組みは龍をあらわしている |
 |
 |
東庭、不離の庭 赤い砂は鴨川の石を砕いたとか
方丈と庫裡を結ぶ渡り廊下に面している |
開山堂 東福寺第三世住持・大明国師の住居跡と言われる |
 |
 |
| 庫裡の公開は初めてとか |
煙突がなく、煙抜きの窓が天井に |
東福寺境内は広く、紅葉で有名な洗玉澗(渓谷)、国宝の三門、金堂、開山堂など。あまり人の多くないこの季節にゆっくりまわるのはいいものです。だけど、三門に上がるのも、通天橋から新緑の渓谷を歩いて見てまわるのも、時間は十分ありましたが、今日はやめました。この後、瑠璃光院と西本願寺でも大分歩くことになりそうで、体力温存しておかなければ。
 |
 |
| 手前は金堂、遠くは三門を横から見たところ |
三門、北側から |
 |
手前は禅堂、遠くは経蔵
たっぷり時間が余ったので、金堂の石段に腰掛けてみなさんと時間待ちをしました |
|