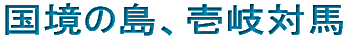

3日目 6月17日(土) 曇り ときどき 雨
全国の天神さんの総元締め。書道の神様、学問の神様として全国で熱烈信仰されている菅公、菅原道真公の墓所。ときの天皇に重用され、官位上り詰めた才気をねたまれ北九州に左遷され、失意のうちに亡くなったとされる。その後、都に疫病はびこり、関係者が次々事故やら病気やらで亡くなる。道真が怨霊となって祟っていると信じられ、神様としてあがめ奉られることになったというのが天神様のいわれらしい。怒りを鎮めるために拝むという神様もあるのですねぇ。
境内はとても広く、後で見学に行った国立博物館も境内の山にありました。
 |
 |
台風で壊れた大鳥居を継ぎ足し継ぎ足し
すぐに新品にしなかった姿勢は好感が持てます
今新しく作ると石が手に入りにくく
コンクリートになってしまうからかもしれませんが |
花菖蒲の池 |
 |
 |
| 大鳥居前の御神牛、いいお顔です |
本堂横の林の中に小さい牛像 |
境内には大きなクスノキが多く、ウメの天神さんというよりクスノキの天神さんの感じ。
昼食は、境内の食堂兼みやげものやで。奥の方には、美人で有名な元芸者さんが始めたというお茶屋さんもあるとか。
境内の山すそにある日本で四つ目の国立博物館の見学をしました。常設展示館は4階。時間が2時間あるというので、2、3階で展示中の琉球展も別途申し込みましたが、4階だけでも2時間では足りないくらいでした。
広い中央部分に大型展示品。小部屋をまわりに14部屋だったか配して、近代から逆に時代を遡って、国宝の陶磁器や美術品。遺跡からの出土品。映像を使って日本の成り立ちを分かりやすく見せるなど、新しい博物館らしいつくりになっています。
|