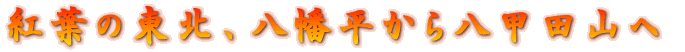

1日目 02年10月 9日(水) 晴
 2002年秋、満席のJAS機は多分ほとんどが紅葉見物ツアー客。1時間40分後仙台に到着して、バスはひたすら北進します。大分寝た後目覚めて、遠くに見える山並みと近くの田畑が延々と続く同じような景色でも、それが東北の景色なら、はるか遠くへ来たもんだという感じがして、この後行く山の中の景色が楽しみでわくわくします。 2002年秋、満席のJAS機は多分ほとんどが紅葉見物ツアー客。1時間40分後仙台に到着して、バスはひたすら北進します。大分寝た後目覚めて、遠くに見える山並みと近くの田畑が延々と続く同じような景色でも、それが東北の景色なら、はるか遠くへ来たもんだという感じがして、この後行く山の中の景色が楽しみでわくわくします。
一関の元酒蔵で昼食。昔、酒造り、今は地ビールをつくって、酒蔵を改装したレストラン、和風レストラン、酒造資料館、みやげ物売り場などで、観光客を呼んでいるようです。地元の人も入れ替わり立ち代り入ってきて、繁盛しています。大きな器にすいとんらしき汁物が出ました。土地でははっとん汁というそうです。昼間は一応アルコールを飲まないことにしているからお茶だけ。隣のおじさんの地ビールがおいしそう。
 左のたわわにみのった実は何か分かりますか。 左のたわわにみのった実は何か分かりますか。
前述の酒蔵レストランの入り口近くに植わっていた柿の木で、豆柿というそうです。実はとても小さくて、直径2センチくらい。
昔酒蔵では殺菌と防腐のために、桶などに柿の渋を塗ったそうで、その渋を取るために敷地内に植えたそうです。何故、他の柿じゃなくてこの豆柿なのかは傍の説明板には書いていませんでした。
私の住む西宮は酒造りの本場、灘五郷のひとつ。そこでも柿の渋を使っていたのかな。豆柿かほかの柿を・・・
 車窓からの景色が関西とは大分趣が違っておもしろい。田んぼはちょうど稲の収穫が終わった後らしく、稲藁がきれいに等間隔にまっすぐに立てて並べてあります。こんな形のは見たことがありません。山はうねうねと低く続き、ときどき右に左に山塊が見えてバスガイドさんが名前を教えてくれるけれど、どれも似ているように見えて覚えられません。東北の背骨というべき山脈が北から南へまっすぐ連なっているかと思っていましたが、そういうのではないようです。 車窓からの景色が関西とは大分趣が違っておもしろい。田んぼはちょうど稲の収穫が終わった後らしく、稲藁がきれいに等間隔にまっすぐに立てて並べてあります。こんな形のは見たことがありません。山はうねうねと低く続き、ときどき右に左に山塊が見えてバスガイドさんが名前を教えてくれるけれど、どれも似ているように見えて覚えられません。東北の背骨というべき山脈が北から南へまっすぐ連なっているかと思っていましたが、そういうのではないようです。
|