
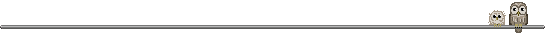
草紅葉の尾瀬ヶ原を訪れたのは、大感動の初めての尾瀬歩きの翌年のこと。尾瀬2度目です。初めはミズバショウを見たいくらいしか考えていなかったけれど、その広さ、自然度の高さともろさ、何よりも景色の美しさ、尾瀬の魅力につかまってしまいました。
是非違う季節の尾瀬を訪れたい願いがかないました。
大阪から乗ってきた大型バスから乗り換えて、鳩待峠に向かう小型バスが高度を上げカーブを曲がるたびに、まわりの山々の紅葉の景色が入れ変わり、車内はオォーと感嘆の声。最近はおばちゃんもウワァーだけじゃないの、知ってました?
オォーにはちょっと驚きました。
黄色から緋色まで微妙な色合いで濃淡混じりあい、自然のままの紅葉の美しさ雄大さ。目も心も脳も、からだ中が喜びます。
 |
前年は山歩き仲間4人でわぁわぁキャーキャーと賑やかに、楽しさうれしさ感動を分かち合えましたが、このときは、それぞれの事情があって私ひとり。
やむなく寡黙に喜ぶしかありません。
その夏、膝を痛めていて不安でした。
膝にくる下りがコースの最初で、最後にそこを登るのが50分。痛くても登りなら大丈夫。長い湿原の木道は平らと分かっていましたから、最悪、途中でリタイアも可能と参加しました。
このとき初めて杖を使いました。
かっこ悪い、邪魔、と思っていましたが、もう1本の足よと知人から勧められ、ヨッピ橋までの往復18キロ、杖を突いて歯を食いしばり、最後は涙をぽろぽろこぼして、足を引きずりながら歩きました。
杖なしで歩きとおすのは無理だったでしょう。 |
これは鳩待峠から大分下りた川上川の岸辺の紅葉
途中の山の中の紅葉はこんなものではありません
錦織の言葉がぴったりでした。 |
|
 |
 |
| 木道の行く手に林が迫って狭くなっているあたりが牛首 |
竜宮でお昼のおにぎり弁当 |
まぁ、草紅葉のすばらしいこと。曇り日の夕日を浴びて、原も山も視界に入るすべてが真っ赤に燃えるのを目にしました。頑張って来てよかった。これでもう2度と来られなくてもいいと納得。大満足。
ところがこれで自信がついて、つらい現実からしばしの逃避と、ミズバショウの頃突然思い立って来てみたり、ニッコウキスゲに埋め尽くされるところを見たいと、やってきたり、この後も何度か訪れることになりました。
|