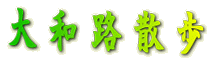
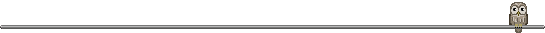
2007年2月12日(月) 晴れ <西大寺からつづく>
この名前の寺が奈良にあることを今日まで知らずにいました。持っていた西ノ京の地図に載っていてきれいな名前だし、4時過ぎだから、外からどんなところか見てみるだけでもいいと、西大寺駅まで戻ってタクシーに乗りました。
車がすれ違えないような細いくねくね道を進んで着いたところは、小さいかわいいお寺だろうという想像に反して、深い森の奥にひっそりと本堂が建っている、広いけれど静かな聖域という場所でした。
 |
 |
| 東門 |
入ってから東門を振り返る |
 |
 |
| 通路の両側がびっしり苔の庭 |
本堂(国宝) |
本尊の薬師如来の左右に日光菩薩月光菩薩。比較的小さい十二神将が6体ずつ階段状の台に乗っていました。狭い壇の上に一列に並んだ仏像は、柵もケースもなく触れる位置。触りはしないけれど、このくらい近くから眺められるのはとってもいい。一番有名なのが伎芸天立像らしく、受付で買える写真はそればかりでした。頭部は天平末期の乾漆造、体部は鎌倉時代の寄木造というけれど、たおやかでふっくらした容姿に違和感はありません。
鎌倉初期の建物だけど、創建は古く天平時代とか。再建されるときはその時代の建築様式が多く取り入れられるのが通例だそうですが、秋篠寺本堂は、古式と鎌倉期の建築様式が混ざった、見たところは純和風の天平の遺風を遺す貴重な建物なのだそうです。
ここは昔から歌人や俳人など文芸関係の人に秋篠の里と親しまれていたそうです。体育だけじゃなく文学も弱かった。知りませんでした。
 |
 |
| 大元堂 |
ふたつの石仏が屋根に覆われ
横の石碑に「大峰山三十三度先達」とある
この寺ゆかりの行者でしょうか |
 |
 |
| 南門 |
南門、中から |
南門の内側左右に、東塔西塔跡があり、東塔のほうは礎石が残っていて触ることができるそうです。小さい古寺を見るだけのつもりだったので、残念ながら、何も知らずに通り過ぎました。
南門から出ると、待ってくれているはずのタクシーの止まっている駐車場が遠そうなので、中を通って帰りました。タクシーの運転手さんによると、この寺は秋の紅葉が有名なのだそうです。その頃また来てみたいな。
|







