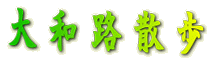
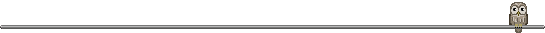
 |
極楽坊ふたつの建物(ともに国宝)、向こう本堂の屋根と
手前禅室の屋根瓦の色が変わっている部分は、
飛鳥寺を移築した当時の行基葺古瓦が使われているという
|
2007年2月20日(火) 晴れ <東大寺2からつづく>
東大寺南大門から出ると、タクシー乗り場に3台待っていました。大分疲れていたしもう帰るつもりでしたが、駅までは近すぎるし、いっそもう少し足を伸ばして、南都七大寺のひとつだったという元興寺(がんごうじ)まで行ってもらいました。大して距離は変わらないのですが。
 |
 |
極楽坊本堂正面から
造りが6間幅で真ん中に柱があるのが珍しいらしい |
入ってきた東門を中から見る |
 受付の人は、世界で一番古い木造建築と、今に教科書の記述が変わる元興寺にようこそと意気軒昂。 受付の人は、世界で一番古い木造建築と、今に教科書の記述が変わる元興寺にようこそと意気軒昂。
建物の外観も面白いし、本堂の中も珍しく、他に誰もいない内部をぐるっとまわってじっくり見せてもらいました。正方形のような感じの堂の真ん中に大きい厨子があって、厨子の大きさに対して信じられないくらい小さい仏像が安置されていました。厨子の裏側は大きな曼荼羅になっていて、特別古いものではないようですが、全体が赤で仏教的な意味は分かりませんが見ていて気持ちのいい絵でした。

建築様式として相当面白いものらしく、柱、組み物、天井、窓、などについて案内書などにも詳しく書いてあります。古代の伝統と中世の新技法の調和において代表的な建物だと。またそれが国宝に指定された理由のようですが、他との比較で面白く思えるほど知らないので、ぱっと見た印象だけ。
真ん中の厨子を囲んで2重の柱列があるのですが、内側の4隅は太い円柱。1辺の中にある2本は角柱。外側もその割合で角柱がまざり、その角柱が創建当初の古材だといいます。
ページトップにおいた屋根の写真は、西日ががんがん当たって赤っぽいですが、中でも赤など色のついたものが古い瓦だそうです。屋根が重なって外から見えない位置に古瓦を利用したというのが、廃物利用らしい感じですが、後世になってそれが脚光をあびるなんて、当時の工人たちが知ったら肩をすくめそうですね。
 創建当初は、同一棟だったのを、仏堂と禅室とに用途によって分けて再建したそうです。今、ふたつの建物の間は離れています。 創建当初は、同一棟だったのを、仏堂と禅室とに用途によって分けて再建したそうです。今、ふたつの建物の間は離れています。
 収蔵庫には、実物の10分の1だという五重小塔(国宝)が天平時代の創建時のままに遺されていました。本物の五重塔も19世紀中ばに焼失するまで天平の息吹を伝えていたそうです。
収蔵庫には、実物の10分の1だという五重小塔(国宝)が天平時代の創建時のままに遺されていました。本物の五重塔も19世紀中ばに焼失するまで天平の息吹を伝えていたそうです。
他にも聖徳太子像などいろいろありましたが、2階別室に庶民信仰の部屋というのがあって、板彫りや木彫の小さい仏像がたくさん並べられていました。
 収蔵庫の前に、大きな礎石が3つ並べてありました。講堂の礎石だそうで、平成10年の発掘作業で見つかったそうです。場所は、ここではなく西隣の町で、そこも本来の講堂の位置からずれているけれど、規模などから講堂の礎石と考えられるそうです。 収蔵庫の前に、大きな礎石が3つ並べてありました。講堂の礎石だそうで、平成10年の発掘作業で見つかったそうです。場所は、ここではなく西隣の町で、そこも本来の講堂の位置からずれているけれど、規模などから講堂の礎石と考えられるそうです。
元興寺はこの奈良町一帯が寺領という、東大寺につぐ大寺だったというけれど、衰退につぐ衰退で、広い寺領に民家が建ち並び、ぽつぽつと遺構や再建坊が別の寺のように建つだけになったようです。
収蔵庫の奥、西南の隅のほうには、地蔵や梵語を彫った石碑、五輪塔などがいっぱい集められていました。庶民信仰厚かったという中世の元興寺にはきっと一帯のこういう仏関係のものが集まったのでしょう。
 |
 |
| 小子房、時代によって、使い方は厨房から庫裏へと変化したけれど、古材を利用しているらしい |
 |
 |
| 禅室を西側から見る |
極楽坊から禅室を北東から見る |
 |
 |
|
西室、寺務所入り口、大きなカメがアクセント |
 |
 |
| 北門 |
世界遺産の石碑
これにはちょっとばかり驚いた
世界遺産の基準って何なのか
もちろん世界に誇る日本の文化遺産ですが・・・ |
 |
駅には1キロもないくらい近い。
道は細い。流しのタクシーなんて来ません。
足は棒、股関節は痛いけど、やむを得ません。
駅まで猿沢の池を通って歩いて帰りました。
だけど、おかげで奈良と言えばの人気写真スポットから
興福寺の五重塔を見ることができました。
|
|