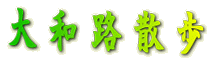
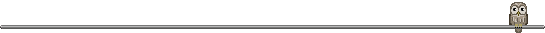
2012年3月31日(土) 雨 のち 曇ったり 晴れたり
いつもの旅行社のパンフレットに仏像めぐりの魅力的な企画がいくつかあったうち、秘仏開陳2体というこのコースに参加しました。室生寺だけは何度か拝観したことがありましたが、他の4ヶ寺は初めてなので、どんなお寺か、どんな観音さまか、あいにくの土砂降りの雨の中、わくわくしてバスに乗り込みました。
 大阪府藤井寺市の道明寺は尼寺でした。小柄だけれど凛とした張りのある声で、尼僧が般若心経を唱え、しばらく説法なさいました。からだは病院だけど、寺は魂を助けるところで、お経を唱え数珠をまさぐって祈ることで魂が救われるというようなお話でした。 大阪府藤井寺市の道明寺は尼寺でした。小柄だけれど凛とした張りのある声で、尼僧が般若心経を唱え、しばらく説法なさいました。からだは病院だけど、寺は魂を助けるところで、お経を唱え数珠をまさぐって祈ることで魂が救われるというようなお話でした。
創建は古く、今も道明寺同様、近鉄の駅名に残る土師(はじ)氏の氏寺として、菅原道真の叔母が住んでいたといいます。菅公左遷の悲劇にまつわる物語もあり、明治初期の神仏分離、廃仏毀釈の嵐の中、寺の移転もあり、奈良や南大阪のどこでも起こったいろんな事件を乗り越えて今に残されている仏像に出会えるしあわせは一入ですね。
 奈良時代から平安時代初期に作られただろうという十一面観音立像は意外に小さく、榧(かや)の木の一木造り、素地仕上げという肌は黒っぽく滑らかです。 奈良時代から平安時代初期に作られただろうという十一面観音立像は意外に小さく、榧(かや)の木の一木造り、素地仕上げという肌は黒っぽく滑らかです。
左手に蓮の葉とつぼみを入れた水瓶を持ち、右手指が軽く動きのある様子で、気品のある顔、立ち姿、うすぎぬの衣の流れるようなひだの重なり、とても美しい。ただ明かりが暗くて、くっきりはっきりと見えなかったのが残念でした。この十一面観音立像は月に2日間のみ公開される秘仏です。
写真は観音像の安置された本堂と、中から見た門です。
桜餅に使われる道明寺粉のはじまりが道明寺糒(ほしい)だったそうで、受付で桜餅を売っていました。
 聖林寺(しょうりんじ)は奈良県桜井市の南部にあり、寺の門までかなり急な坂を傘をさして上りました。本堂には目指す十一面観音ではなく、驚くほど大きい真っ白地蔵の坐像が鎮座しています。これは江戸時代中期に巨石を彫刻した子安延命地蔵菩薩だそうで、安産・子授けに霊験あらたかとか。 聖林寺(しょうりんじ)は奈良県桜井市の南部にあり、寺の門までかなり急な坂を傘をさして上りました。本堂には目指す十一面観音ではなく、驚くほど大きい真っ白地蔵の坐像が鎮座しています。これは江戸時代中期に巨石を彫刻した子安延命地蔵菩薩だそうで、安産・子授けに霊験あらたかとか。
本堂でしばらくお寺の若奥さんという感じの女性から説明があり、走りまわる幼児が鉦をたたいたり、台によじのぼったり、ちょっとびっくりでしたが、お寺ですから叱るということもないのでしょうか。
 その後、本堂を出て鉄筋別棟の階段を上って国宝十一面観音立像だけが大きいガラスケースに入っているのを拝観しました。
その後、本堂を出て鉄筋別棟の階段を上って国宝十一面観音立像だけが大きいガラスケースに入っているのを拝観しました。
かのフェノロサによって再発見激賞されたという像は、国内では彫刻作品としての評価が低かったそうです。
寺伝によると、聖林寺の創建は奈良時代、談山神社の別院として建てられたとか。
十一面観音立像は、三輪山の大神神社の神宮寺であった大御輪寺から移され、本尊ではない寺宝となっているということのようです。 木心乾湿造りで金箔が残っています。よく似た像が、今日最後5寺目の京田辺市、観音寺の十一面観音像だそうで、多分,
同時期に、同じ東大寺官営工房で造られたのではないかと考えられているそうです。道明寺のふっくら豊満でかわいく見える観音さまより大分大きく、顔と姿が男性的。左手に蓮のつぼみと葉を入れた水瓶を持ち、右手指先に動きがあるのは、十一面観音像に共通の特質のようです。三輪山、大神神社、神宮寺との結びつきの強さは、関係古文書が多数残っていることでも分かるそうです。門前から、大和盆地の古墳群、三輪山、箸墓が一望できます。今日は雨で三輪山は遠くにうすく見えるだけですが。 木心乾湿造りで金箔が残っています。よく似た像が、今日最後5寺目の京田辺市、観音寺の十一面観音像だそうで、多分,
同時期に、同じ東大寺官営工房で造られたのではないかと考えられているそうです。道明寺のふっくら豊満でかわいく見える観音さまより大分大きく、顔と姿が男性的。左手に蓮のつぼみと葉を入れた水瓶を持ち、右手指先に動きがあるのは、十一面観音像に共通の特質のようです。三輪山、大神神社、神宮寺との結びつきの強さは、関係古文書が多数残っていることでも分かるそうです。門前から、大和盆地の古墳群、三輪山、箸墓が一望できます。今日は雨で三輪山は遠くにうすく見えるだけですが。
奈良県でも三重県に近い宇陀郡の室生寺。一昨年の平城遷都1300年記念事業の一環で、室生寺も五重塔の初層開扉など特別拝観がありました。それは春と秋のほんの短期間でしたが、その年は、金堂内陣に居並ぶ仏像を外の縁側からではなく、外陣まで入れてもらえたのが長かったようでした。今回も、同じように外陣からの拝観で、間近から見る大きい五仏像はもちろん、十二神将(もとどおり10体になっていましたが)もはっきり細かいところまでわかって感激でした。
それにしてもいつ拝観しても、ちょっと小さめの室生寺十一面観音立像はあでやかで、若々しく女性的な美しい観音さまです。
 |
 |
本堂、今日は中に入るのをやめました、
ちょっと疲れてしまいました
|
濡れて滑りそうな石段を二つ目登りました
下の屋根は金堂(仏像ならぶ)です |
|
 |
 |
室生川
|
|
雨やまず、五重塔は石段の下から、私もです |
 |
 |
室生寺は建物も仏像も見るべきものが多く、天気がよければ1時間ももらっているのだから、奥の院まで行く人もいるくらいだけれど、今日はさすがに、この雨では、五重塔の下でもういいわと言う人が結構いて、私も、上って来た石段を下りなければならないのも恐いし、この後まわる2ヶ所がどんなところか分からないし、余力を残しておこうと、しばらく休憩所で座って休みました。もったいない感じはしましたが、5ヶ所もまわらないときにゆっくり歩きまわることにします。
 光明皇后に縁の深い総国分尼寺という奈良市内の法華寺は、格式高い寺だというにおいを色濃く漂わせていました。春と秋に特別公開される期間がある以外は分身という写しを見せてもらえるようです。私たちには、翌日4月1日から1週間行われる雛会式なる行事の前日という恩恵があったらしく、特別開扉の十一面観音立像の前に、善財童子の小像が五十五体並んで祀られているところを見せていただきました。珍しい雛たちを見られたのはよかったです。 光明皇后に縁の深い総国分尼寺という奈良市内の法華寺は、格式高い寺だというにおいを色濃く漂わせていました。春と秋に特別公開される期間がある以外は分身という写しを見せてもらえるようです。私たちには、翌日4月1日から1週間行われる雛会式なる行事の前日という恩恵があったらしく、特別開扉の十一面観音立像の前に、善財童子の小像が五十五体並んで祀られているところを見せていただきました。珍しい雛たちを見られたのはよかったです。
高さが1メートルの、光明皇后の姿をうつしたとか、光明皇后自身の作とか、いろいろ伝わっているらしいありがたい十一面観音立像そのものは、いつもは閉じられている厨子を開けて、前を順に歩かせてもらいましたが、照明が暗くて、あまりよく見えませんでした。添乗員さんがどこからかうつして来られて、バスの中で一生懸命に説明してくれた今にも歩き出そうとするかのように右足親指をぴんと立てた姿というのや、優美な翻波式衣文とか、見えませんでした。 本などの写真で見る限り、榧(かや)材の一木造り、素地仕上げの肌は、木の肌そのものの色合いのようですが、ただ黒いばかりで、足元は見えず、残念でした。 でも、蓮の葉がばらばらに背を覆っているような光背は分かりました。他にはこんな光背はないでしょうね。 本などの写真で見る限り、榧(かや)材の一木造り、素地仕上げの肌は、木の肌そのものの色合いのようですが、ただ黒いばかりで、足元は見えず、残念でした。 でも、蓮の葉がばらばらに背を覆っているような光背は分かりました。他にはこんな光背はないでしょうね。
二つある庭園のうち、華楽園は100円追加して入れるというので、行ってみました。サンシュユが満開で、椿も残っていましたが、この庭園の見所は浴室(上写真)だそうで、光明皇后が薬草を煎じその蒸気で1000人の垢を流したという`からふろ’。中は見られず外観だけでしたが。
もう止みそうだと傘を持たずにバスを降りたけれど、まだまだ降り続いていて、濡れてしまいました。
やっと雨が上がって青空が現れたからか、最後の京田辺市、観音寺の印象が一番強く残っています。住職の説明が明確で明かりが十分だったことも大きいですね。まっすぐに立った十一面観音立像の姿は優美というより均整の取れたしっかりした仏像という感じを受けます。桜井市聖林寺のとよく似ているといいますが、本尊として厨子の中に安置されているからか、より威厳があって美しい印象です。
寺は、元は普賢寺と呼ばれる大寺で、いまも大御堂と呼ばれるそうです。最盛期には諸堂13、僧坊20を数えた大伽藍を持っていたという大寺が、山すそに小さい本堂ひとつポツンと建つだけの寺になっています。
 |
 |
| 例年なら今頃は、菜の花と桜の競演でさぞかし美しい参道なのでしょう |
 |
 |
焼失と復興を繰り返して、今こんなにも小さくなった寺
1300年前にここで修行した僧たちの思いがこの辺りに残っているような気がしてきます |
 |
 |
| きっとそこいらに諸堂の瓦や礎石などの遺構もあるのでしょう |
東大寺二月堂お水取りの竹がここから送られていたとか
その復活の地となっているそうです |
今日めぐった国宝十一面観音立像5体は、いずれも8世紀から9世紀ころの製作と想像されるという古い観音さまばかりでした。姿かたちもよく似ていました。
個人ではとてもまわれないややこしそうな場所だったり、秘仏開帳も団体だから待つことなく丁寧な案内があって、行ってよかった。いいツアーでした。
|