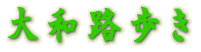
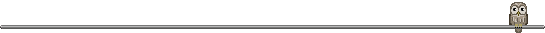
 冬は、スキーや冬山登山を楽しまれる人も多いでしょう。ちょっとだけ歩きたいハイキング好きには寂しい季節に、正月明けから毎週山の辺の道を歩くツアーがありました。 冬は、スキーや冬山登山を楽しまれる人も多いでしょう。ちょっとだけ歩きたいハイキング好きには寂しい季節に、正月明けから毎週山の辺の道を歩くツアーがありました。
桜井から天理を経て奈良公園まで、日本一古い国道といわれる三輪山麓30キロの道を4回に分けて歩こうというのです。
奈良で積もるのは珍しいという雪の中、トレッキングシューズにカッパ着て傘さして、雪景色を楽しみながら、道沿いの寺社や廃寺、陵墓、みかんや柿の果樹園をぬって歩きました。
面白い歴史ガイドさんがついてくれました。70歳近いご老体で、胃を取ってしまってから体力が落ちたといいながら、舌鋒鋭く、そんな大声でとこちらが気になるくらい、「存在すらはっきりしない初期の天皇の陵墓です。」なんて。
 |
 |
大神(おおみわ)神社
雪の中、拝殿には大勢の参拝者がいて賑わっている
|
檜原神社の三つ鳥居 |
ご神体が三輪山という日本人の自然崇拝の信仰心が生きているらしい。決して高い山ではないけれど、手付かずの原生林は、うっそうとして神宿るらしき荘厳さを漂わせているように見えます。
檜原神社も、三輪山をご神体として、本殿はなく鳥居の両脇に小さい鳥居を組み合わせた三つ鳥居という珍しい鳥居がありました。三輪神社にも同じものがあるそうです。初期の神社は何でもあり、素朴に思ったとおりの造りだったのじゃないでしょうか。
 |
 |
三つ鳥居の拡大写真
|
| いつもは奈良盆地が見晴らせ、大和三山も見えるとか |
|
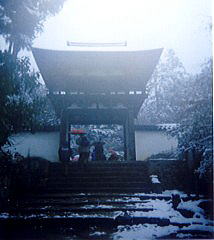 左の写真は長岳寺の鐘楼門。これも非常に珍しい建築物だそうです。 左の写真は長岳寺の鐘楼門。これも非常に珍しい建築物だそうです。
面白いガイドさんからどこでも詳しい説明を受けましたが、メモもとらないし、片っ端から名所らしきところに入って、それが次々続くのですからどれが何やら。第1回だけは雪景色につられて写真が少し残っていますが、2回目以降は写真もほとんどなく、記憶ははるかかなたにかすんで・・・
大神神社のように、今も沢山の参拝の人でにぎわっているところもあれば、かつては日本で一番古い市があって賑わったという道の合流地点が、すっかりさびれているとか。栄枯盛衰、歴史の歩みを見てきた道が、今も広げられず車が通らず、よく残ったなぁと感慨が湧きます。
|