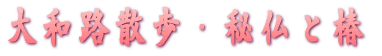
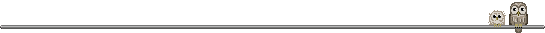
2010年3月17日(水) くもり 後 晴れ
白毫寺(びゃくごうじ)は春日山から南につづく高円山山麓にあり、近鉄奈良駅からは4.5キロだそうで、元気なときでも歩いては往復するだけで精一杯。あちこちまわりたいし、歩きは境内と帰り道の2~3キロにしたいから、今日も電車を降りたらタクシー。運転手さんも知らない伝光寺を探し、福智院とまわって白毫寺へ。
 |
 |
ここに来るまでに2つ石段を曲がって上ってきて
はぁ~、この上にまだこの石段、悩みつつ上ると → |
藪椿の散り椿、よし、もう少しがんばってみるか |
 |
 |
| 古びた土塀と山門が、申し訳ないけどいい感じに見える |
あれからまた随分上ってきたよ、奈良の町がよく見える
秋になるとこの石段の左右に紅白の萩が咲き乱れるとか |
 |
 |
| 本堂とその前にある緋車椿の木 |
緋車椿 |
 |
 |
| 宝蔵 |
宝蔵横からの眺望、遠く生駒山までよく見える |
本堂真ん中に鎮座していたのがどんな仏像だったか記憶にないが、前方向かって左に勢至、右に観音菩薩がかがみ加減に、片や手を合わせ、あるいは蓮花型の器を持っている姿が愛らしい。あちこちで見る、今日も伝光寺にもあった聖徳太子二歳像も安置されているが、本尊はじめ主な諸仏は後ろの宝蔵にある。閻魔王坐像と興正菩薩叡尊坐像(白毫寺中興の祖といわれる叡尊晩年の像)が興味深い。
今日のお地蔵さんめぐりにこだわったわけではないが、こちらの地蔵菩薩立像は、鎌倉時代の作というが、色がまだ剥げ落ちるまでいっていなくて、光背の彫りも見事。生きた人間のようなお顔が慈悲深く感じられる。
 |
 |
石仏の道
どこまで続くかと思ったが、本堂横を少し上ったり下りたり |
| 下りたところに、右の不動明王とある石仏が・・・ |
後ろの火炎がなくて寂しそう |
 |
 |
| ひとつの幹から五つの色合いの花が咲く五色椿 |
 |
満開とはいかなかったけど、左上と中の方には咲いているよ
写真をクリックすると説明板が別画像で出ます |
寺名になっている「白毫」というのは仏の眉間にあって光明を発したとされる白い毛のことを指すらしい。
|
























