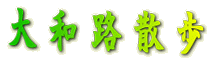
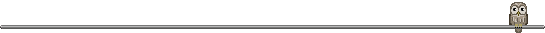
2010年10月29日(金) 晴れ のち 曇り
今年年初から華々しく開けた平城遷都1300年祭は、メイン会場の平城京跡での各種イベントも大盛況だったようです。人込みが苦手で、各寺社でそれぞれに特別公開されたところをぽつぽつ見て歩いただけでしたが、今年の奈良あるきは私にとって超豪華版となりました。最後を締めくくることになりそうですが、一番手近な奈良公園内興福寺に行ってきました。
 近鉄奈良駅から東大寺や国立博物館への通り道としてしか認識していなかった興福寺が国宝の宝庫だと知った2007年1月の初拝観以来3度目。 近鉄奈良駅から東大寺や国立博物館への通り道としてしか認識していなかった興福寺が国宝の宝庫だと知った2007年1月の初拝観以来3度目。
今回は、10月9日〜11月23日の間、初層開扉特別公開の五重塔、春に改装なった国宝館、本来の在りようらしい東金堂と後堂、短期公開北円堂の4つの建物に入って拝観見学しました。
藤原鎌足を祖とする藤原氏の氏寺として隆盛を極めた興福寺ですが、時代の変遷とともに諸堂は何度も火災に遭い、復興再建を繰り返したそうです。現在の五重塔は室町時代(1426年)に建てられた6代目。国宝です。
まったく並ばずに入ることができました。中は、太い心柱を中心に南に釈迦三尊像、西に阿弥陀三尊像、北に弥勒三尊像、東に薬師三尊像。それぞれの如来像に脇侍が2体ずつ、12体全部が坐像で割合に小ぶりですが、表情、衣装、足元の邪鬼など精妙に作られ、今後もうお目にかかることもないと思って、じっくり拝観させてもらいました。
見えている部分の心柱は板状のものに四面覆われていましたが、床下が一部開けられて、大きな花崗岩の上に直接のせられた太い円柱が見えました。京都・東寺の五重塔床下は、色鮮やかに絵が描かれていましたが、興福寺はいかにも建物の基部というあっさりした感じです。
 東金堂に居並ぶ国宝仏像たちはいつ見てもすばらしく、後堂と言っていましたが、初めて須弥壇の裏側にまわって、本尊、阿弥陀如来像の背面板絵とその前に、いつもは公開することのない正了知大将像が50年ぶりに戻され祀られたのを見ることができました。 東金堂に居並ぶ国宝仏像たちはいつ見てもすばらしく、後堂と言っていましたが、初めて須弥壇の裏側にまわって、本尊、阿弥陀如来像の背面板絵とその前に、いつもは公開することのない正了知大将像が50年ぶりに戻され祀られたのを見ることができました。
1017年の火災時に踊り出て焼失を免れたとされる伝説の持ち主で「踊り大将」と信仰厚かったそうです。
後堂公開も今回だけらしく、五重塔と東金堂とその後堂だけで拝観料1000円は高いと思いましたが、いつも見られる東金堂表の諸仏にしても国宝が多く見事な彫像に感動深く、けちけちしてはいけないと自戒しました。
 後ろの扉が開けられているので明るく良く見えました。五重塔でもそうでしたが、建物内部だけじゃなく、まわりの柵よりも中は写真撮影禁止で、東金堂の後堂から出た後、カメラを向けたら笑いながら制止されました。仕方ない。柵から出て、隣の五重塔を入れて1枚撮りました。 後ろの扉が開けられているので明るく良く見えました。五重塔でもそうでしたが、建物内部だけじゃなく、まわりの柵よりも中は写真撮影禁止で、東金堂の後堂から出た後、カメラを向けたら笑いながら制止されました。仕方ない。柵から出て、隣の五重塔を入れて1枚撮りました。
諸仏をはじめて見たときの感想はこちら。
国宝館は、この春大改造され、以前より格段に見やすくなりました。 文化財に悪影響が少ないLED照明が採用されたそうで、仏像の多くがガラスケースなしというのがいいですね。
人気の阿修羅だけじゃなく、ほかの八部衆も十大弟子立像(6体現存)も、 見違えるほどはっきり細部までよく分かり、展示方法は大事だと分かります。
以前見たことがあるのはもちろん、いつもは南円堂で秘蔵されているらしい法相六祖坐像が6体揃って並んでいました。当時の名僧と呼ばれた人たちの像でしょうが、寺伝の名称には混乱があったようで訂正されるべきものもあるという文を見たことがあります。頭塔で始めて知った僧玄鈁の像が中心に座していましたが、法相六祖には入っていないことが多いらしい。
国宝館だけは行列になっていて、入館するのに20分並びました。見るべきものが多いし、混雑もしているし、ここでは疲れ果てました。
 北円堂は五重塔より期間が短く、10月23日〜11月7日の間だけ特別公開。 昨年今頃も帰ってきた阿修羅像を仮金堂で公開した際、同じく公開していて、
40分並んで拝観したのですが、今日は全然行列はなく、何度でも本物に接するのは得がたい感動体験です。 北円堂は五重塔より期間が短く、10月23日〜11月7日の間だけ特別公開。 昨年今頃も帰ってきた阿修羅像を仮金堂で公開した際、同じく公開していて、
40分並んで拝観したのですが、今日は全然行列はなく、何度でも本物に接するのは得がたい感動体験です。
何年も準備中の感じだった中金堂がいよいよ着工中で、いわば興福寺の中心が再興されるわけですね。5〜7年で完成したら、仮金堂に安置されている仏像たちが戻って、壮麗な天平伽藍として加わるようです。その頃元気でまた来れるかなぁ。無理だろなぁ。

|

