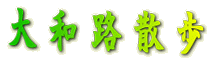
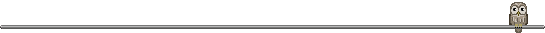
 |
転害門(てがいもんー国宝)
鎌倉時代に大修理が行われたが、天平の様式をよく遺しているらしい |
2007年2月20日(火) 晴れ
正倉院の外構は平日見学させてくれるというので、絶好の散歩日和、いつもの大和路散歩に出かけました。
大仏殿の北西の方にある正倉院に行くのなら、東大寺境内の北西角にある転害門(てがいもん)に先ず行こうと、タクシー乗り場に行きかけましたが、前回、頭塔まで乗ったタクシー、別に感じが悪かったわけじゃないけれど、駅前でずっと待ってて、ワンメーターじゃかなわんだろうなと、バスを探しました。案内所があるから聞けばよかったのに、ま、いいやと市内循環の東大寺方面からまわるバスに乗ってすぐに降りました。
足の具合の悪いときには、運転手さんの心配よりも自分の心配をするか、案内所でめんどくさがらずに聞くべきでした。降りたところが氷室神社前。
 |
 |
| 枝垂桜が何本も、花の頃にはすごい人でしょう |
舞殿 |
 ここは初めてなのでよかったんだけれど、そこから転害門の遠いこと。時速1〜1.5キロくらいじゃなかったか。
亀よりも蟻よりものろのろと人も車も滅多に通らない、奈良じゃのうというような古い土塀の路地を北へ、くねくね曲がりの道なりに歩きました。 ここは初めてなのでよかったんだけれど、そこから転害門の遠いこと。時速1〜1.5キロくらいじゃなかったか。
亀よりも蟻よりものろのろと人も車も滅多に通らない、奈良じゃのうというような古い土塀の路地を北へ、くねくね曲がりの道なりに歩きました。
 つい大通りを避けて横道に入るからずいぶん遠回りになりましたが、おかげで広い東大寺境内の西から北方面は大分分かりました。 つい大通りを避けて横道に入るからずいぶん遠回りになりましたが、おかげで広い東大寺境内の西から北方面は大分分かりました。
 曲がって曲がって突き当たりに大仏殿を小さくしたような建物が見えます。地図では戒壇院でしょう。だけどこの石段を登る元気がわきません。
曲がって曲がって突き当たりに大仏殿を小さくしたような建物が見えます。地図では戒壇院でしょう。だけどこの石段を登る元気がわきません。
 天気はいいし、人はいないし、最高の散歩道だったんだけど。この朝のはじめの歩きで大分足に無理を掛けてしまいました。 天気はいいし、人はいないし、最高の散歩道だったんだけど。この朝のはじめの歩きで大分足に無理を掛けてしまいました。
ここは今度にしようと横の緩やかな地道の坂を上り、お坊さんたちの寮という感じの建物のあるところに出ました。少し手前の建物の前に大きな箒のようなものがあって、修二会準備と書いてあったから、お水取りに使うたいまつだろうかとしげしげ見てしまいました。
小さい門をくぐって石段を下り車の通る道に出ると、電柱に鹿の絵が貼ってあります。このあたり、鹿の交通事故が多いのでしょうね。
 古い街道という感じの片アーケードの、今も主街道らしい通りを進むと、こんなところにという感じで国宝の門がそっと建っていました。このページのトップ写真です。普通の町の一角という場所ですが、扉のない門の中には境内らしい広々した草原が見えました。
門に入ることはできません。 古い街道という感じの片アーケードの、今も主街道らしい通りを進むと、こんなところにという感じで国宝の門がそっと建っていました。このページのトップ写真です。普通の町の一角という場所ですが、扉のない門の中には境内らしい広々した草原が見えました。
門に入ることはできません。
東大寺の観光客でここまで来る人はほとんどいないようです。それにしても広い!
最盛期には伽藍もさることながら、いったいどれだけの僧侶がいたのでしょう。強大な勢力で僧兵も養い、その力ゆえに政治権力者との争いもあり、12世紀の興福寺・東大寺の焼き討ちとなったそうですから、その後武士による政治権力によって庇護され再興再建があり、今もこの広大な境内を保っているなんて、不思議な感じがします。
右写真は転害門の向かって右端の柱です。こんな節だらけの大柱、はじめて見ました。風雨にさらされてよけい節々が目立つようになったのでしょうが。
来た道を少し戻って、大仏池と呼ばれる大池、といってもあまり水がない干上がった印象の池の横をまた北向きに歩きます。大池越しに大仏殿が見えて、背景は若草山を含む春日山とくれば絵になりますねぇ。ひとり、絵筆をとって熱心に描いている人がいました。絵ごころのある人はいいなぁ。
 |
 |
見学用入り口は白壁に沿って右のほう
この門にも、宮内庁の立てた説明板がある |
入門は無料、校倉造の建物が貴重な国宝なのだから
見る価値は高いと思うが、あまり人がいなかった |
 |
 |
| 中門の外の池から全景を見る |
中の門を入ると全体をカメラに入れるのは無理 |
想像していた通り立派な大きい校倉造。感激です。こちら側(東向き)に扉が3つ。流れるように簡潔な屋根が古代らしさを見せています。古さではこの間見せてもらった唐招提寺の経蔵が上のようですが、この中で守られて1300年間も古代の小物や布までも保存されていたというのは、この湿気の多い日本の奈良にあって信じられないことです。校倉造を考えて造り出した人が生きていたら、どんなに誇りに思うでしょう。
鐘楼のあるほうへ行こうと歩いていると、先日二月堂から降りてきた道と合流しました。前回、このあたりはあわてて大仏殿に入って他は見なかったのですが、大仏殿の裏、北側に大きな礎石が何列かになって並んでいるところがありました。講堂跡だそうです。いつだったかテレビでこういう礎石の上に直接柱を置く和式の建築法が地震に強いとやっていたのを見て、大いに納得しました。火事にはやられるけれど、地震で建物がやられたとは、古代以来の建築物で聞きませんね。
東側にある丘に登る猫段と呼ばれる石段をえっちらおっちら登りました。
 |
 |
| 猫段 |
| 講堂跡の礎石 |
まわりは桜の木
今はこの辺は静かですが、花の頃の賑やかさが想像できます |
 |
 |
 |
屋根の形がそりが大きく、日本離れしています。
鐘楼も、梵鐘もその大きさは並大抵じゃありません。
中に人間が何十人も入れそう。
どうやって釣っているのかと見上げてみると、
太い梁に穴を開けてそこに鐘本体の釣り下げ部を通し
上でそれをとめる工夫がしてあるのでしょう。
多分安定させるためでしょう、
他に2本太いワイヤーを梁にまわして4ヶ所釣ってありました。
屋根と梁を支える組んだ木が美しい。 |
 |
 |
| 俊乗堂 |
行基堂 |

鐘楼のある丘をぐるっと諸堂をまわって、どこへ行くのかのぼりの石段があったので、またのぼりかぁとぼやきながら杖をついて1段ずつ上りました。なんだか見たような光景・・・三月堂(法華堂)の横に出てきました。
礼堂と正堂をくっつけてひとつにした建物とは、前回帰宅後分かったことなので、この方向からの写真はありませんでした。これはよく分かりますね。くっつけたところは不要になったのに樋のようなものが残っているのですよ。
くたびれたと思ったら、この右横に食堂があって、二組の人が入って行ったし、ちょっと休憩と昼食を。にしんそばを食べて元気復活。
前回素通りした四月堂の千手観音を拝み、裏から入って正面から見なかった手向山神社を正面から撮って、三月堂の諸仏には後ろ髪ひかれる思いでしたが、ひも靴を脱いだり履いたりが大変だから、今日は止めました。

再び鐘楼のある丘まで下って、そこから北向きの石段を降りたところに、大湯屋がありました。
奈良時代創建の大湯屋だけど、他の堂塔と同じように12世紀の兵火によって焼かれ、俊乗上人による再建。内部に鉄の湯船があるとか。
この道を左のほうに進むと、なんとまた、二月堂から降りる道につながっていました。
 |
 |
| 指図堂 |
左写真左隅、僧の像 |
 |
 |
| 戒壇院への道 |
戒壇院、門から本堂を見る |
 |
 |
| 前庭 |
中から門を見ると、下に朝一番に歩いてきた道が見える |
 |
写真を撮っていると、通りかかったお坊さん?こんにちは、と声を掛けてくださいました。
東大寺の戒壇院は、後に唐招提寺の開祖になった唐僧鑑真が聖武天皇をはじめ多くの公家に戒を授けたところであるけれど、今の建物は13世紀の再建になるもの。
中を拝観しました。
堂の中いっぱいになる大きさの壇があり、その上に多宝塔がのっています。その中に小さい2体の仏像の偽物が祀られ(本物は収蔵庫内に安置)、四方に四天王がにらみを利かせる配置になっていました。 |
| 壇のまわりは板敷きになっていて、ぐるっと一周できたのは楽しかったけれど、靴を履くのが大ごとで、股関節の痛い人には靴カバーがほしいところね。 |
鏡池越しに見る中門と大仏殿
鹿が近くにいないことを確かめてベンチに座って一休み
| 次は、日本でいや世界で一番古い木造建築?元興寺(がんごうじ)へ → |
|




 ここは初めてなのでよかったんだけれど、そこから転害門の遠いこと。時速1〜1.5キロくらいじゃなかったか。
亀よりも蟻よりものろのろと人も車も滅多に通らない、奈良じゃのうというような古い土塀の路地を北へ、くねくね曲がりの道なりに歩きました。
ここは初めてなのでよかったんだけれど、そこから転害門の遠いこと。時速1〜1.5キロくらいじゃなかったか。
亀よりも蟻よりものろのろと人も車も滅多に通らない、奈良じゃのうというような古い土塀の路地を北へ、くねくね曲がりの道なりに歩きました。 つい大通りを避けて横道に入るからずいぶん遠回りになりましたが、おかげで広い東大寺境内の西から北方面は大分分かりました。
つい大通りを避けて横道に入るからずいぶん遠回りになりましたが、おかげで広い東大寺境内の西から北方面は大分分かりました。 曲がって曲がって突き当たりに大仏殿を小さくしたような建物が見えます。地図では戒壇院でしょう。だけどこの石段を登る元気がわきません。
曲がって曲がって突き当たりに大仏殿を小さくしたような建物が見えます。地図では戒壇院でしょう。だけどこの石段を登る元気がわきません。 天気はいいし、人はいないし、最高の散歩道だったんだけど。この朝のはじめの歩きで大分足に無理を掛けてしまいました。
天気はいいし、人はいないし、最高の散歩道だったんだけど。この朝のはじめの歩きで大分足に無理を掛けてしまいました。 古い街道という感じの片アーケードの、今も主街道らしい通りを進むと、こんなところにという感じで国宝の門がそっと建っていました。このページのトップ写真です。普通の町の一角という場所ですが、扉のない門の中には境内らしい広々した草原が見えました。
門に入ることはできません。
古い街道という感じの片アーケードの、今も主街道らしい通りを進むと、こんなところにという感じで国宝の門がそっと建っていました。このページのトップ写真です。普通の町の一角という場所ですが、扉のない門の中には境内らしい広々した草原が見えました。
門に入ることはできません。























