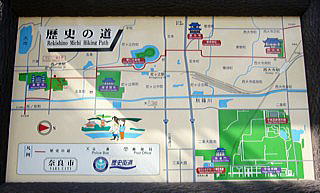8世紀半ば、鑑真和上によって戒律を学ぶ私寺として創始された唐招提寺は、鑑真亡き後、弟子たちの時代に、金堂や五重塔を備える大伽藍へと発展したそうですが、奈良の大寺院の例に漏れず、衰退と復興の歴史を繰り返し、今は大復興期なのではないでしょうか。 金堂は平成の大修理のまっ最中で、約10年掛けての大修理。完成は2年半後だとか。南大門を入るとすぐに異様な波板状壁の大きな建物があり、金堂を解体修理中覆う建物とその前に素屋根の小部屋のようなものがあって、修復中で見られない宝物などをコンピューターグラフィックスで映像で見られるようになっていました。
初めて来たのは40年位前。その後1度来ていますが、どこも同じでしょうけど、この間の変化のすごいこと。講堂にごろごろ放り出されていたように見えた仏頭、頭なしの壊れた仏像等は、新宝殿に大切に納められています。
おばちゃんひとり、写真を撮りまくっているのを見たからか、50代くらいの男性が声を掛けてきました。どこから来たかというのですが、すぐに本題に移られたので、自説を開陳するにいい相手と思われたのでしょう。唐招提寺とは直接関係のない話で、宗教嫌い歴史好きといって、古事記日本書紀はうそばかりと、固有名詞をたくさん挙げて感心させたいようでしたが、私の知っている範囲のことだとわかる相槌を打っていたら、離れてくれました。いろんな人がいます。
本尊の裏に無造作に置かれていたと40年前に思い込んだ鑑真和上坐像は、興福寺一乗院の宸殿を移築したというたいそう立派な御影堂奥深くの厨子に、今では東山魁夷画伯による68面の障壁画に囲まれて、おさまっているのです。鑑真和上坐像は、本尊の裏側に置かれたことはなく、ずっと開山堂(今では旧開山堂と呼ばれる)に安置されていたそうで、いったい何と思い違いしていたのでしょう。教科書の写真と同じ像がこんなところにあるなんてと、驚いたのですが・・・
講堂は大きくて、中の仏像たちが小さく見えるほど。近年、平城宮跡が発掘調査されて、いろいろわかってきているらしいが、現実には、見た目ただの草原。その平城宮から奈良時代末期に移築した建物がここの講堂だそうで、切妻造りから入母屋造りに変えたり須弥壇を作って仏堂しつらえにしたりと改めた点もあったけれど、本体はそのまま残った、平城宮唯一の遺物なのだそうです。
金堂解体修理のため、内陣に安置されていた盧舎那仏坐像、千手観音立像、薬師如来立像の三体の巨大仏像(いずれも国宝)が修理工房に移されていて見られなかったのが残念至極。 |