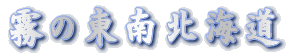

2日目 7月3日(水) 霧雨ときどきくもり

宿の窓の外がぼんやり明るくなって目覚めると、相変らず雲は低く垂れ込め、霧に覆われた周囲の山とさざなみの立つ湖面が幻想的な青さで静まりかえっています。然別湖(しかりべつこ)だぁ…大雪山系で唯一の自然湖だぁ…しばらく夢見心地で見とれました。時刻は…さすがに日本列島東端。午前3時半。
今日歩くのはあの山の裏側か。嬉しさがこみ上げます。
しかし残念無念。この旅の一番の目的、然別湖の奥の小さな湖、あと数十年でまわりからの土砂で埋まって消えてしまう運命の東雲湖(しののめこ)へのハイキングは、雨の中では岩場が危ないからと、近くの森の散策に代えられてしまいました。
リバーウォッチングと称して、川の中に胸までのゴム長をはいて入って、横を泳ぐ珍しい清流の魚を見るコースも設定されましたが、気温が10℃そこそこなんてところです。どんなに好奇心に燃えようと冷え性の私には無理。元気のいい人たちがそちらに行きましたが、ほとんどの人は森の散策コースを選びました。
 |
 |
| エゾマツ、トドマツの原生林 |
幹にまっすぐ凍裂跡、トドマツ |
案内してくれた若い女性ネイチャーガイドさんは、私たちのレベルに合わせて、やさしく分かりやすく、どんな質問にも丁寧に答えてくれ、にわか仕込みの知識でも、植物がその姿であることの意味、戦略などが分かってとても楽しい散策でした。
森のあちこちで静かに壮絶な生存競争が繰り広げられているのを目の当たりにできます。
トドマツは冬期水分を逃がすのがうまくできなくて、零下40度にもなるこの森では、身に持っている水分が凍り、生きている木がバーンと音をたてて裂けるのだそうです。それでも自力で修復して成長しつづける木も多いとか。その生命力に感動してしまいます。
 左写真の前列3本のトドマツは倒木更新の成功者で、前世代の木が倒れた後、仲良くその木を肥やしとして育ったいわば三兄弟というわけです。 左写真の前列3本のトドマツは倒木更新の成功者で、前世代の木が倒れた後、仲良くその木を肥やしとして育ったいわば三兄弟というわけです。
このあたりは日本で一番の低温記録を持つ土地だそうで、冬は零下40度以下になったこともあるとか。森の中を通っている立派な道路は冬季半年以上凍結して通行禁止になり、鹿の道になるそうです。鹿も歩きやすい方がいいんだって…笑っちゃいました。
夏の今でも滅多に車なんて通っていない。この道路を作ったためにまわりの生態系は崩れて、日当たりの好きな広葉樹がまるで街路樹のように道に沿って生い茂っています。広葉樹の成長は早いから今はこんな景色だけれど、数十年すれば、今、足元でひょろひょろしている針葉樹が大きく育って、本来の森のすがたになるのだそうです。
 然別湖に注ぐ唯一の川、ヤンベツ川のほとりではオジロワシのペァが近くの草原から羽音高く飛び立つところを目撃できて大感激。そのすぐ後で、のどのオレンジ色がよく目立つキビタキが、間近の枝から枝へ鳴きながら飛び移って、まるで自分を誇示するかのようでしたが、この行動は巣の近くにやってきたものを追い払うための行動だそうで、かわいい姿を見られたのは嬉しかったけど、悪かったねぇ。ごめんね。
然別湖に注ぐ唯一の川、ヤンベツ川のほとりではオジロワシのペァが近くの草原から羽音高く飛び立つところを目撃できて大感激。そのすぐ後で、のどのオレンジ色がよく目立つキビタキが、間近の枝から枝へ鳴きながら飛び移って、まるで自分を誇示するかのようでしたが、この行動は巣の近くにやってきたものを追い払うための行動だそうで、かわいい姿を見られたのは嬉しかったけど、悪かったねぇ。ごめんね。
川の石の裏にはトビゲラがしがみついています。清流でしか生きられないカゲロウの幼虫。水溜りにはエゾアカガエルとおたまじゃくしも。
 |
|
| 稚魚を放流 |
ミヤベイワナ |
1時間ほど森の動植物の生態などを聞きながら、現役のけもの道(エゾシカの足跡がついた道)をゆっくりと歩いて、湖のそばへ帰ってきたら、ネイチャーガイドさんが小さく「ラッキー。」というのが聞こえました。ここ然別湖にしかいない、発見者の宮部博士の名をもらったという天然記念物ミヤベイワナの稚魚を放流するトラックがちょうど着いたところでした。そんなに簡単に見られるものではないのでしょう。稚魚といってもかなり大きく、15〜20センチくらい。成長すると30〜40センチにもなるとか。ゆうべホテルの夕食に出たオショロコマという魚はここだけのものではないようです。
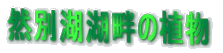
色鮮やかな浜辺の原生花園の花たちに比べて、森の中は白い花が多い。
 |
 |
 |
| カラマツソウ |
ゴゼンタチバナ
葉っぱが6枚になると花が咲くとか。確かに4枚のには花がない |
|
 |
 |
 |
マイズルソウ、羽を広げて舞う鶴の姿
からという・・・これは親子鶴かな |
ズダヤクシュ
喘息の薬ということから |
イラクサ、葉の端のとげが刺さると
すごくいらいらするらしい |
 |
 |
 |
| 鹿にかじられたフキ |
マタタビ |
トドマツの新芽? |
 |
 |
 |
| ウワミズザクラ |
ヤナギの仲間 |
コウゾリナ |
マタタビが虫の活躍する季節だけ、目立たない小花だけじゃだめだと葉を白やピンクに変えて虫を誘い子孫を残す戦略は、植物が花を作っていく進化の過程なのでしょう。何万年か後にはきれいな白とピンクの花に…?
車窓からの北海道らしい風景
 午後はバスでの移動だけ。硫黄山近くのイソツツジの大群落が見事でした。
午後はバスでの移動だけ。硫黄山近くのイソツツジの大群落が見事でした。
 ほとんど寝ていましたが、車窓からも北海道らしい景色が見えます。ひたすらまっすぐの道路。放牧の牛や馬。 ほとんど寝ていましたが、車窓からも北海道らしい景色が見えます。ひたすらまっすぐの道路。放牧の牛や馬。
阿寒湖、カムイコタンなどで、ちょっと休憩しました。
牧草地に転がしてある色とりどりのテープで巻いたものは、牧草を俵型にぎっしり詰めたものだそうです。昔、北海道らしい風景といえば、サイロのある風景でしたが、牧草が醗酵しているサイロに入って作業中にガス中毒事故になったこともあるそうで、やはり作業量もすごいからでは?今ではこの俵型牧草をこうして外に放っておいて、必要になったら直接牛舎に運んで食べさせるそうです。貯蔵倉庫も要らないし、誰かが考えて広まったのでしょうね。すごいアイディア。
今夜は、目的の東海岸までの途中、屈斜路(くっしゃろ)湖畔のホテルで泊まります。
|

