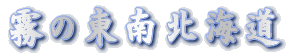

3日目 7月4日(木) くもり
 今日は、北海道の最東端、根室地方の珍しい風景の中を歩きます。泊まっただけの屈斜路湖畔のホテルを出発後、360度地平線が見えて、丸い地球を実感できると言われる開陽台に立ち寄りましたが、濃霧では遥かな地平線どころか足元もおぼつかないほど。 今日は、北海道の最東端、根室地方の珍しい風景の中を歩きます。泊まっただけの屈斜路湖畔のホテルを出発後、360度地平線が見えて、丸い地球を実感できると言われる開陽台に立ち寄りましたが、濃霧では遥かな地平線どころか足元もおぼつかないほど。
 知床半島と根室半島の真中あたりから、えびのような形に突き出た小さな半島、日本最大の砂嘴(さし)、野付半島を有名なトドワラを見ながら湿原と原生花園を歩き、観光船に乗って向かい側の尾岱沼(おたいぬま)に渡りました。トドワラは、森林を形成していたトドマツが海水の浸食で立ち枯れていく現象です。 知床半島と根室半島の真中あたりから、えびのような形に突き出た小さな半島、日本最大の砂嘴(さし)、野付半島を有名なトドワラを見ながら湿原と原生花園を歩き、観光船に乗って向かい側の尾岱沼(おたいぬま)に渡りました。トドワラは、森林を形成していたトドマツが海水の浸食で立ち枯れていく現象です。
湾内だけれど、風が強くて、小さい船が結構飛ばすので、揺れました。時々波間から顔を出すゴマフアザラシを探すのが忙しい。顔を出してちょっとの間こちらをまん丸おめめで見てすぐにもぐります。かわいい。霧が少し晴れたら、かすかに国後島(くなしりとう)の島影も見えました。

陸に近づくと、尾岱沼の風物詩、打瀬舟(うたせぶね)の北海シマエビ漁が間近で見えます。浅い海の海草を傷つけない舟だとか。帆船ですよ! カッコい〜い。
お昼に真っ赤に茹で上げられたこの北海シマエビと、近くの名物、花咲蟹を食べさせてもらいました。おいしい!今の時期と秋の一時しか漁がないそうです。ラッキー!
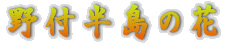
 |
 |
 |
 |
| チシマアザミ |
アザミの仲間? |
シコタンキンポウゲ |
エゾカンゾウ |

午後は、今も成長と退行が進む自然の聖域、春国岱(しゅんくにたい)ウォーク。
 知床方面から根室半島の付け根まで海流によって運ばれた砂が長い年月をかけて堆積して、3列の砂州ができているところ。 知床方面から根室半島の付け根まで海流によって運ばれた砂が長い年月をかけて堆積して、3列の砂州ができているところ。
海水混じりの風蓮湖(ふうれんこ)とオホーツク海を隔てて、広大な砂丘に海水に強い植物が育っては枯れて湿原となり、草原となり、ついにはアカエゾマツの純林、トドマツやナラの生い茂る大森林になった推移を同時に見ることができます。
大森林を形成していた砂州が海水の浸食でもとの海に戻っていく様がトドワラやナラワラという形で目にすることができす。
 |
 |
 |
| オオシバナ(大塩場菜) |
ウミミドリ(海緑) |
エゾツルキンバイ |
 |
 |
この植物たちは塩分に強く、
最初に砂丘に
草原を形成するそうです。
エゾツルキンバイは
あまり塩分の強いところでは
育たないとか。 |
| アッケシソウ(厚岸草) |
上左は塩水の入ってくる浜辺にできた高層湿原です。右はどんな高山深山の原生林かと思うほどのうっそうたる森ですが、海抜8メートル。春国岱で1番標高の高い場所です。
森林から出るとすぐ前は海。草原に立ち枯れの白骨の木。なんとも不思議な光景です。
この森も草原も太古の昔というほど古くからあったわけではなく、一番古くて海から遠い森の砂州で三千年くらい前。最も新しい海側の草原で千五百年から千年くらい前にできたそうです。

 カモメの群れと一緒に波打ち際にいた嘴が赤くて長いミヤコドリ。テトラポットの上で孤独に海を眺めるオジロワシ。近くの枝でさえずるカッコウ。意外に低い声でした。私は見逃してしまいましたが、ヒバリ、ベニマシコ、カワラヒワもいたそうです。 カモメの群れと一緒に波打ち際にいた嘴が赤くて長いミヤコドリ。テトラポットの上で孤独に海を眺めるオジロワシ。近くの枝でさえずるカッコウ。意外に低い声でした。私は見逃してしまいましたが、ヒバリ、ベニマシコ、カワラヒワもいたそうです。
エゾシカやタンチョウも、自然観察員さんが望遠鏡を持ち運びながら案内してくれ、見せてもらうことができました。エゾシカやタンチョウはバスの車窓から何回も近くで見ましたが、写真に撮ることはできませんでした。

クマゲラが餌のアリを食べるためにつついた木は、かわいそうなくらい穴だらけ。
サルオガセという苔の仲間は、栄養を吸って木を枯らすと信じられていたけれど、最近の研究で、木が枯れても自分は生きていて、木の栄養を取って枯らしているわけではないと分かったそうです。

20数年前、然別湖へ行く途中の森が、どの木もこのとろろ昆布のようなものにぶら下がられて、子どものころ見た魔法使いのおばあさんが出てくる西洋絵本のようで気味が悪かったけれど、今回はあまり見ませんでした。空気のきれいなところでしかサルオガセは育たないそうで、少なくなったことを喜んでいいとは言えないようです。
 |
 |
| ナガバツメクサ |
マイズルソウの実 |
花咲岬
茹でて赤くなった背中の模様が花のようだからと花咲蟹(はなさきがに)の名のある蟹に因んで名づけられたという花咲岬。岬に付き物の灯台が建っていて、ずっと霧笛を鳴らしていました。きっとここでは霧笛がやむときのほうが珍しいのではないかとか、岩に襲い掛かる荒波と暗い海の色が北の海だなぁ、と感じさせられます。
 車輪半分のような放射状節理が珍しく、天然記念物の根室車石と立て看板がありました。 車輪半分のような放射状節理が珍しく、天然記念物の根室車石と立て看板がありました。
濃い霧でよく見えない急な崖にたくさんいたウミネコが印象に残りました。
|