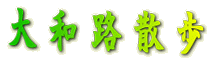
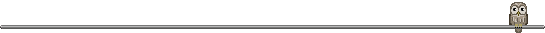
 |
夢殿
この時期、ご本尊の救世観音像が厨子の中に安置されたまま拝観できる |
2008年4月9日(水) 晴れ <法隆寺・西院伽藍からのつづき>
 上御堂から下りてくると左写真の道になる。左に無料休憩所の建物。そこを通り過ぎて右側遠くのベンチに腰掛け、お茶を飲んで持ってきていた大判焼きを食べて休憩。 上御堂から下りてくると左写真の道になる。左に無料休憩所の建物。そこを通り過ぎて右側遠くのベンチに腰掛け、お茶を飲んで持ってきていた大判焼きを食べて休憩。
今度こそ、駅に戻って電車に乗って帰るつもりだった。もう歩けない。くたびれた。ところがまた、むくむくと夢殿の横の枝垂桜は満開じゃないかの思いが湧いてきて、しばらく休憩して元気が出たところで、よっこらしょっと東院伽藍への道を進んだ。昨年来たときよりも、参道が短く見える。初めてというのはどうしてあんなに遠く見えるんだろう。横に並んだ子院の屋根に乗っている鬼瓦が面白くて、疲れは吹っ飛んだ。
 |
 |
| 気力を振り絞って東に向かう |
東大門、外からは普通の屋根に見えるが・・・ |
 |
 |
東大門は“三棟造”の天井を持つ
見せかけの複屋根らしい |
東大門を潜り抜けると東院伽藍夢殿の屋根が見える |
 |
 |
| 鬼瓦が鬼の顔でなく、動きのある唐獅子の姿というのは珍しいのでは?(子院・安養院) |
 |
 |
| どんな意味があるのか、横の桃が気になる (律学院太子堂) |
 |
 |
| 左右でこれだけ形状が違う鬼瓦も珍しい?(宗源寺) |
 |
 |
| 東院伽藍入り口、四脚門 |
手水が鳥の形、鳳凰かな |

鐘楼と右は東院廻廊
遠くから見ると屋根が特別大きく見える
このページトップの夢殿の中で何世紀もの間、白布に包まれて人の目に触れることなく秘仏とされてきたのを、岡倉天心とフェノロサが明治17年か19年かに開扉して、公になったとされる救世観音像。金堂の仏像が金銅仏であるのに対して、救世観音は樟材の一木造り。初めて拝観したが、金箔が残り1300年昔の仏像とは信じられない美しい姿。
あちこち古いお寺の仏像を見せていただいたが、木製の仏像は傷みが目に付き、屋外に出ていたというのはひどいささくれや裂け目が目立ち、法隆寺の仏像がどれも傷みも無く保存されてきたのは大変な努力の積み重ねだったのだろう。



法隆寺で一番遅咲きなのだろうか。東院伽藍の南東隅の枝垂桜が満開。がんばって歩いてきてよかったぁ。来週来たって葉桜になっているだろう。
伽藍内の建物配置などは、昨年のページをご覧ください。こちら。
このあと、四脚門までタクシーに来てもらい、駅まで帰るはずが、またまた欲を出して、法輪寺、法起寺とまわって法隆寺駅に帰ったのでした。→
|

