
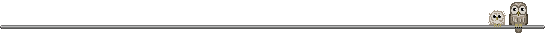
17日目 3月25日(火) 晴れ (1)
今日はクスコを出発してどんどん高所へひたすらバスが走ります。最終目的地は、チチカカ湖。海抜3800メートル。途中4300メートルの峠を越えるというのが、怖いようなうれしいような。朝から何度も深呼吸をします。期待と不安がない交ぜの興奮気味の心理状態です。バスに酔いそうな予感もするし、実際にバスのなかでは軽い頭痛がしてドキドキ。それは数回の深呼吸で治まり心底ほっとしました。
道路はパンアメリカンハイウェイ。北米から南米を、ところどころ切れているけれど、縦断して走る国際道路だというのですが、未舗装のただの田舎道がつづきます。列車の線路とウルバンバ川と並行して走っています。この道路も、数年前までは相当のガタガタ道だったそうです。かのフジモリ元大統領が、整備してよくなったとか。旅の前半の道のいい、時間の短い道中のときに、たいてい前のほうの座席におさまっていたので、最後に長時間(8時間、正味6時間半くらい)走るのは、後の席でガタガタポンポン。先に楽した報いです。腹をくくりました。
 クスコを出て最初に見えてきた村は、クスコのオレンジ色に統一された屋根瓦全部を製造する村でした。ふたつめの村では住民の80パーセントがパンつくりで生計を立てているとか。村による完全分業。直径30センチくらいのパンを添乗氏が買ってみんなに少しずつ味わわせてくれました。乾燥地だからフランスパンみたいに表面固く作るかと思いましたが、意外や柔らかくておいしい普通のパンです。ペルーのパンはホテルで食べる小ぶりのパンもなかなかおいしい。どちらかの村の名がオロペッサ。書きなぐりのいい加減なメモで・・・ クスコを出て最初に見えてきた村は、クスコのオレンジ色に統一された屋根瓦全部を製造する村でした。ふたつめの村では住民の80パーセントがパンつくりで生計を立てているとか。村による完全分業。直径30センチくらいのパンを添乗氏が買ってみんなに少しずつ味わわせてくれました。乾燥地だからフランスパンみたいに表面固く作るかと思いましたが、意外や柔らかくておいしい普通のパンです。ペルーのパンはホテルで食べる小ぶりのパンもなかなかおいしい。どちらかの村の名がオロペッサ。書きなぐりのいい加減なメモで・・・
読んだ紀行文ではどの人も、列車で行ったらしいので、何でバスで?峠がより高いのでは?と要らぬ心配をしました。列車はバスほど揺れないだろうと思うだけで、終点のチチカカ湖湖畔の町プーノやその前のフリアカ駅の治安の悪さ恐ろしさを知れば、列車でなくていいのですが・・・添乗氏によれば、列車では11時間かかり、時に1〜2時間遅れることがざらだそうで、そういえば峠で列車が故障、1時間遅れて夜着いたとも書いてありました。3〜5時間も違えば、多少ガタガタしても、それはバスのほうがいい。
 ワカラペイ(泣いている子供の涙)という小さい湖があったり、関所だったという赤い石を積み上げて造った城壁が見えたり。車窓の景色が変わり、退屈したり眠くなったりすることはありません。 ワカラペイ(泣いている子供の涙)という小さい湖があったり、関所だったという赤い石を積み上げて造った城壁が見えたり。車窓の景色が変わり、退屈したり眠くなったりすることはありません。
 ときどき軽い高山病らしい頭痛がしますが、深呼吸を数回すれば治まります。ありがたいことにバスに酔うこともありません。 ときどき軽い高山病らしい頭痛がしますが、深呼吸を数回すれば治まります。ありがたいことにバスに酔うこともありません。
ある地点から家々の屋根が、瓦葺からトタン屋根に変わりました。この辺ではよくヒョウが降るからだといいます。すごい音でしょうに、瓦じゃ割れるのでしょうか。
 2時間おきくらいにトイレ休憩に止まります。サン・パブロという村は楽しいところでした。トイレ使用料が無料だというから、トイレのまわりに並んだ小さな民芸品の店で、それぞれ何か小物を買いました。Noさん奥さんの買われた何かの木の実らしい小さなマラカス風の絵柄つき楽器がすてき。$1とか。今度どこかで売っていたら買おうと、そばの人とそう言い合いましたが、結局それ以後どこにもありませんでした。ベビーアルパカの毛足の長い、楽しげな絵柄の壁掛けを、Saさんが買っておられるのを見て、私も同じものを衝動買いしました。<みやげ物のページはこちら> 2時間おきくらいにトイレ休憩に止まります。サン・パブロという村は楽しいところでした。トイレ使用料が無料だというから、トイレのまわりに並んだ小さな民芸品の店で、それぞれ何か小物を買いました。Noさん奥さんの買われた何かの木の実らしい小さなマラカス風の絵柄つき楽器がすてき。$1とか。今度どこかで売っていたら買おうと、そばの人とそう言い合いましたが、結局それ以後どこにもありませんでした。ベビーアルパカの毛足の長い、楽しげな絵柄の壁掛けを、Saさんが買っておられるのを見て、私も同じものを衝動買いしました。<みやげ物のページはこちら>
 
サン・パブロの道路を隔てた向こうでは、本物の市が開かれていて、野菜・果物・肉など、物々交換だそうです。イキトスでのアジア風大雑踏の大市場でもなく、今までによく見た観光客用民芸品を声高に売り込むのでもなく、山高帽にスカートの重ね着、アジア風面立ちのおばさんが地べたに座り込んで、無愛想に、自分ちで採れたらしい何種類かの小粒のジャガイモをころがしてあります。これまた無愛想な少年が小ぶりのりんごにかぶりついています。
背中に色鮮やかな大きな袋を背負った姿を絵や写真で見ていましたが、実際に目にしたおばさんは顔がとても大きく、ほとんど5頭身。精悍な浅黒い顔立ちを別にすれば、私と同じ。Hiさんの言うように、モンゴロイドだと思われます。DNA鑑定でも日本人と同じと出たそうです。
クスコでもよく見かけた山高帽のこのスタイルは、最初にイギリス人がチチカカ湖あたりに入ってそれが広まったから、この辺が発祥地なのだそうです。私たちは喜んでシャッターを押し続けますが、何百年前と変わらない生活なのでしょう。きっと想像を絶する貧しさだろうと、道々車窓から見たアドベ(日干しレンガ)でできた、木造でいうなら掘っ立て小屋ともいうべき家から人が出てくるところを見て、なんとも言いようのない思いにかられました。
 何も自分たちと比べてどうこう言うことはないと思うけれど、昔の人々の歴史のあとや自然のすばらしさだけを観光するために、ずかずか彼女たちの領域に入り込むことの不遜を思わざるを得ません。 何も自分たちと比べてどうこう言うことはないと思うけれど、昔の人々の歴史のあとや自然のすばらしさだけを観光するために、ずかずか彼女たちの領域に入り込むことの不遜を思わざるを得ません。
南米では、観光客以外にほとんど笑顔を見ることはありませんでした。大人も子どもも。
でも民族衣装を着た男性が、子ども連れの若い女性に何か話しかけると、女性もまわりの無表情だったおばさんたちも、みなにこにこ。生活が余りに厳しいと、人間、笑顔になれないのかと思いかけていましたが、こちらまでうれしくなりました。
|



