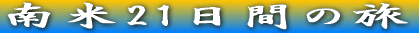
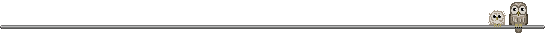
9日目 3月17日(月) うすぐもり
 今朝はゆっくり10:00出発。1日中リマの市内観光。旧市街地の中心は、重厚な石造りの建物がまわりを占めている公園。新市街は高級住宅地の明るい街並み。 今朝はゆっくり10:00出発。1日中リマの市内観光。旧市街地の中心は、重厚な石造りの建物がまわりを占めている公園。新市街は高級住宅地の明るい街並み。
砂漠の街リマでは、会員厳選のゴルフクラブコースを目の前にしたマンションが最高級マンションなのだとか。緑いっぱいというのは相当贅沢なことのようです。

公園はどこも花いっぱい。明るくきれい。噴水、花壇、花の木。時期はずれでも2、3本、南アフリカで有名なジャカランダの紫色の花が咲いています。四季がはっきりしないのでよくあることだそうです。公園はいつも手入れが行き届いています。
ブラジルもアルゼンチンも都市の公園はそうでした。貧しい国という先入観から意外の感がありますが、中心の公園をお金をかけてきれいにするのはどこの国でもそうでしょう。(
植物、都市)
 スペイン統治時代の建物は、石づくりの優美な細工の建物に、外から中は見えませんが、中からは外が見えるという繊細な木彫のバルコニーがついていて、当時のステータスだったそうです。見事だとは思いますが、ちょっとアンバランスな感じをうけます。
スペイン統治時代の建物は、石づくりの優美な細工の建物に、外から中は見えませんが、中からは外が見えるという繊細な木彫のバルコニーがついていて、当時のステータスだったそうです。見事だとは思いますが、ちょっとアンバランスな感じをうけます。
写真の真ん中奥にみえる横丁といってもそこそこ広い賑やかな通りは、街1番の繁華街。だけど現地の人も危ないという泥棒、スリ、ひったくり、強盗が横行する通りで、別名泥棒通りとか。日本人も金持ちとして狙われ、すでにもう何度も観光客がそういう目にあっていて、私たちは連れて行ってもらえませんでした。抱きつき強盗、ケチャップ強盗など、注意をそらして一瞬の犯行だそうです。
バスが交差点で信号待ちしている間に、窓の外を物売り(子供、男、女、おばあさんまで)がうろうろして、声をかけてきます。目をあわさないように、荷物は上の荷台か座席の下に。
時には窓ガラスを割って手を伸ばして盗られるそうです。信じられない話だけれど、バスの中の灯りを消して、信号が少なくても結構車の多い通りを、みんなでブーブー警笛を鳴らして、あまりマナーもいいとは言えないで走る様子を見ると、なるほど後進国とはこういうことかと思わされました。
 国として豊かではなく、貧富の差が激しく、失業率が高く、多分教育も十分ではない人たちが、生きるために地方から都会に流れてきて、ブラジルと同じく、どんどん高い不便なところへ上がって暮らしているようです。
国として豊かではなく、貧富の差が激しく、失業率が高く、多分教育も十分ではない人たちが、生きるために地方から都会に流れてきて、ブラジルと同じく、どんどん高い不便なところへ上がって暮らしているようです。
以前は鉄道網が今よりは有効に働いていましたが、どの線も鉱物資源を運ぶために敷設されたので、全部リマと最終地点を結ぶだけで、横のつながりはまったくなかったそうです。今は、1路線だけかろうじて1日1回運行されているとか。それも値段が高く、ペルー国内移動は、飛行機かバスがほとんどだそうです。
| 博物館は見たこともないインカやプレインカの展示品でいっぱい |
黄金博物館は、頑丈そうな門扉に物々しい警戒。外のガードマンは警官に見えるくらいです。これが観光ポリス?門の横から中に入ると、広い庭にはみやげもの屋というより、インカ風プレインカ風に細工してある宝飾品の店が5〜6軒、1軒ずつ別の建物を構えています。博物館の建物の中は、1階にまずズラーと戦闘具の展示。蒐集した人の趣味だからなんとも言いようがありませんが、武器製造業者?武器商人?単なる趣味?
 アブミ式土器からはじまって、石器、織物。プレインカからインカの遺物が所狭しと壁1面のガラス張り展示ケースに順に並べられています。よくも個人でこれだけ集められたものだと感心します。完璧なミイラに驚きました。頭蓋骨に四角に穴が開けられているのは頭の外科手術あとだといいます。やたら細長い頭蓋骨は、身分の高さを誇示するために、赤ちゃんの時からそんな格好に包帯状のもので巻いて、形作ったそうです。 アブミ式土器からはじまって、石器、織物。プレインカからインカの遺物が所狭しと壁1面のガラス張り展示ケースに順に並べられています。よくも個人でこれだけ集められたものだと感心します。完璧なミイラに驚きました。頭蓋骨に四角に穴が開けられているのは頭の外科手術あとだといいます。やたら細長い頭蓋骨は、身分の高さを誇示するために、赤ちゃんの時からそんな格好に包帯状のもので巻いて、形作ったそうです。
やたら首を長くしたり、足を小さくしたり、人間って、特殊な身分を示すために、ずいぶんけったいな無理なことをしたんだなぁと感じます。ミイラは布に包まれただけで、砂のなか3メートルほどの深さに埋まっていたそうです。1年中ほとんど雨が降らない地域だから、髪の毛もそのまま、皮膚も崩れることがないこんなに完全なミイラができるのでしょうか。
プレインカ時代の区分とか、それぞれの特徴とか、この黄金博物館では、われらのガイド具志堅さんが、やっと本来のガイド業ができるとばかりに、いきいきと熱心に早口に、一生懸命に説明してくれます。個人の蒐集物の展示だから、時に間違った説明や違う区分に入れられたりということもあるということでした。
彼はリマに来てから9年。ペルーに来るきっかけはなんだったのか分からないけれど、とにかくペルーがどんなに好きか。ペルーの文化をどれほど誇りに思っているか。体中から噴出しています。
空港やホテルや街で、食事や見物、買物などの手配。旅行業者としての煩雑な仕事。観光客や旅行社の無理な要望・・・多分。だけど、いつもにこにこ。冗談めかして、皆様がこうして来て下さるおかげで、私はここにいることができます、とおっしゃいます。そう?そうなんだ。添乗員さん、あなたもそう?そんな風に考えたことある?ないでしょうね。ま、実際添乗は大変だけど。
お昼のアンティーク調のレストランのメニューは、ビエッタ・デ・トーヨ(チキンスープ)、アローン・スコーン・バルシコス(海産物のパエリア)、ペルー風ドーナッツに黒糖シロップかけ。どれも特においしいとは感じませんでしたが、米の粒のような、多分とうもろこしの入ったスープ。これはおいしい。食事についてきたアルコール系飲み物は、ピスコサワー。ペルーの代表的カクテルとか。白ぶどうの蒸留酒ピスコに、卵白、レモンを入れてシェイク。シナモンがかかった白い泡のお酒。 口当たりよく、適度にアルコール度が感じられて、食前酒にはいいのですが、量が多くて、食事中にずれこむと、甘くて困りました。
チチャという飲み物はお酒だと本には書いてありましたが、ジュースだと言われました。多少発酵していても、日本でいうお酒の部類には入らないのでしょうか。普通の家で作るそうだから、衛生的に問題があるのか。ちょっと飲んでみたかったのですが・・・
 ミニバスで通り過ぎながら見ただけですが、古い建物が今も残って現役で使われている通りがありました。建物の建て替え等には規制があって、歴史的建物の多い通りとして保存しているそうです。その壁の落書きのすごさ。どこにも困った奴らはいるものです。 ミニバスで通り過ぎながら見ただけですが、古い建物が今も残って現役で使われている通りがありました。建物の建て替え等には規制があって、歴史的建物の多い通りとして保存しているそうです。その壁の落書きのすごさ。どこにも困った奴らはいるものです。
その通りの家の入り口はとても背が高いのです。植民地時代、スペイン人たちは騎乗のまま家に入る習慣をそのまま持ち込んだのだそうです。背の高い白人が大きな馬に乗って、背もかがめずに入っていく姿が目に浮かびます。聞くまで、入り口の高さには気がつきませんでした。歴史的な視点で見ていなかったことに気づかされました。
日本人に有名な天野博物館のほうがあとだったから、はじめて見たときほどの感動はなかったのですが、説明してくれるのは、説明ボランティアの日本人青年でした。みんな熱心に説明を聞き、時には質問もしました。
薄い引き出しに丁寧にしまわれている布は、正倉院のよりも古いのにきれいに保存されています。乾燥している土地だからでしょうか。それでも、発見時より赤の色など、変色してきているそうです。ガーゼのような薄い布に絞り染めがされていて、今ではその技法は分からないのだとか。複雑な文様の美しさ、技術の確かさに驚きました。文様は直接生活に必要というわけではありません。美意識が技術の発達を促したのでしょう。文字のなかったインカでは、ひもを結んだキープというものがあって、結び目や色で情報の記録になったそうです。案外細いひもで、たこ糸程度。これも残念ながらほとんど意味は解明されていないそうです。
時間つぶしのようでしたが、海岸段丘の公園に行きました。パルケ・デ・アモール(愛の公園)。なんとそのものずばり。でっかいピンクのモニュメントは、男女が抱き合っているもの。なんともおおらかな国民性。日本ならきっと大騒ぎになるでしょう。実物も3組。そばへ行っても離れません。
前の海は太平洋なわけです。私たちの日本に、何にも阻まれずにただ水でつながっているのですが、実感はありません。海の色は、意外に暗く、フンボルト海流なる南極からの寒流が流れていて、水温は低いそうです。その海流に乗って、プランクトン−−−いわしとやってくるから漁業が盛んで、カタクチイワシの漁獲量が今は世界で2位とか。昔1位と学校で習ったことがありましたが、今は2位ですか。
ペルーといえば、アンデス。私たちには山地のイメージが強いのですが、山岳地帯、海岸部の砂漠地帯、ジャングル地帯と大きな差のある3地域を持っているのがペルーだそうです。
夕食は、中華レストランで。でも日本での中華料理とは似て非なるもの。日本風チャーハンがなつかしい。
チシャモラーダという紫とーもろこしのジュースをとる人がいました。
このごろ毎回つくようになったピスコサワーでいいとほかをとらず、
記念にピスコサワー、他の人のビール、今日はじめて知ったペルーの国民的飲み物インカコーラを
並べて撮影しました。 |
 |
| 左からインカコーラ、ピスコサワー、ビール |
今日で都市部はおしまい。明日からは地方へ。ナスカの地上絵、奥アマゾンのジャングル、マチュピチュ遺跡、チチカカ湖とつづきます。後半のほうが、高地で高山病の不安はありますが、はるばるペルーまで来ないと見られない景色のところ。旅の半ばにしてますます、世界の不思議と謎に出会うことになる明日からを思って、期待に胸が高鳴ります。
|


 スペイン統治時代の建物は、石づくりの優美な細工の建物に、外から中は見えませんが、中からは外が見えるという繊細な木彫のバルコニーがついていて、当時のステータスだったそうです。見事だとは思いますが、ちょっとアンバランスな感じをうけます。
スペイン統治時代の建物は、石づくりの優美な細工の建物に、外から中は見えませんが、中からは外が見えるという繊細な木彫のバルコニーがついていて、当時のステータスだったそうです。見事だとは思いますが、ちょっとアンバランスな感じをうけます。
 国として豊かではなく、貧富の差が激しく、失業率が高く、多分教育も十分ではない人たちが、生きるために地方から都会に流れてきて、ブラジルと同じく、どんどん高い不便なところへ上がって暮らしているようです。
国として豊かではなく、貧富の差が激しく、失業率が高く、多分教育も十分ではない人たちが、生きるために地方から都会に流れてきて、ブラジルと同じく、どんどん高い不便なところへ上がって暮らしているようです。


 ミニバスで通り過ぎながら見ただけですが、古い建物が今も残って現役で使われている通りがありました。建物の建て替え等には規制があって、歴史的建物の多い通りとして保存しているそうです。その壁の落書きのすごさ。どこにも困った奴らはいるものです。
ミニバスで通り過ぎながら見ただけですが、古い建物が今も残って現役で使われている通りがありました。建物の建て替え等には規制があって、歴史的建物の多い通りとして保存しているそうです。その壁の落書きのすごさ。どこにも困った奴らはいるものです。

