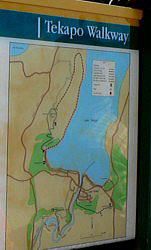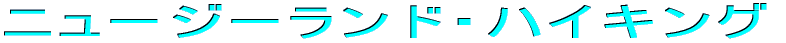
3日目 2006年2月6日(月) 曇り 後 晴れ
| クライストチャーチからテカポ湖へ、のどかな牧草地を見ながら進む |
今日は1日忙しい。5:00am起床、7:00am出発。 クライストチャーチから離れるにつれ広い牧草地に牛、馬、羊が放牧されている風景ばかり続くようになります。朝早いからか牧草地の中に埋め込まれているらしい散水機から撒かれた水が細いたくさんの噴水のよう。ときどき長さ100メートル以上もありそうな巨大な棒状の散水機?散水車?が真ん中を中心にしてぐるっと回りながら散水しているところもあって、なんとも農業経営規模の大きさを知らされます。
馬にだけ毛布のようなカバーが掛けられていました。馬は夜露や寒さに弱いのかと思ったら、紫外線対策だそうです。そういえば、ニュージーランドは南極に近く、オゾン層の破壊が進んでいて、日本の5〜6倍の紫外線を浴びると知って、たっぷり日焼け止めを塗っていたのですが、昨日1日うす曇りの日に街の中をうろついただけだのに、おでこと頬が赤くなっていました。だけど、なんで馬だけ?牛や羊はいいの?
 |
 |
| トイレ休憩に立ち寄ったおみやげやさん |
その前の大きな木のある石の家 |

ここへ来るまでの曇り空からは考えられない青空。左の小高い山が今から登るマウント・ジョン。右端に小さく見える家は“善き羊飼いの教会”。その右に教会を見つめるバウンダリー犬の像が建っています。
山頂までハイキングする予定。上からはどんな風に見えるのか。マウント・ジョンの向こうの景色はどんな風なのか。歩き通せるかしらの心配よりも、このお天気。この景色。わくわく感が高まります。
 |
 |
小さい教会の内部はこれで全部、まん前の窓から見えるテカポ湖とサザン・アルプス
飾り気のない小さい十字架とその向こうの景色、初期開拓者たちの祈りが聞こえるようです |
 |
 |
| 湖畔の村の日本食レストランでスモークサーモン丼 |
 |
| 教会を見つめるバウンダリー犬 |
2日前にクラシックカーのレースがあったとか
公道を走るたくさんのクラシックカーにはびっくり |
おいしいサーモン丼(ちらし寿司)で腹ごしらえもできて、ハイキングに出発。植林だという落葉松林の中を登ります。
道はずっと整備された歩きやすい道が続きます。ただ登り一方なので息があがり、ハァハァ言ってしまいますが、苦しくもつらくもありません。
テカポ湖の標高は710m。マウント・ジョンは1030m。標高差300mあまり、約5キロをゆっくり登っておりました。
 |
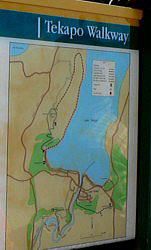 |
右拡大案内図、湖の左側真ん中あたりを
小さくくるりとまわって下ります |

植栽の落葉松はそろそろ終わり、マオリの人も手を焼いたという草ばかりの茶色の世界。遠くにサザン・アルプスが見えてきました。このあたりは年間降水量が600ミリと比較的乾燥地帯で、見渡す限りの茶色の大地は無理もないことのようです。ハイキング道の横にはそれでも少し自生の植物もありました。<こちら>

テカポ湖側から見えなかったアレキサンドリア湖、向こうに雲をかぶってサザン・アルプスが連なる

アレキサンドリア湖の手前に牧草研究畑、乾燥地に適した牧草を作る研究らしい
テカポ湖の周辺、ここから見えているあたり一帯はミスター何とか(ガイド氏はちゃんと名前をおっしゃったけどいつものように瞬時に脳から消えてしまった)という個人の土地だそうで、まるで違う星にでも来たかと思うような茶色の大地と真っ青の湖。羊1頭放牧されている様子もなくて、まさにこれがここの自然。150年前にこの土地をどうやって手にいれたのか、まさか、ここ僕んちって柵を作ったわけでもないでしょうけど、そのときご先祖様は、一面の放牧場を夢見られたのでしょう。この荒涼たる景色も、牧草の研究が進んで、100年もしないうちに一面の牧草地に変わっているかもしれませんね。
こうしてハイキングできるのは、そのミスター何とかの好意によるものだそうです。
 |
 |
天文台をくるっと巻いてちょっと休憩
名古屋大学天文台らしい |
← 下りは直下へ下りる
テカポ湖とテカポ村が眼下に |
 |
 |
| マウント・クックのまわりだけ雲が遠慮してるよ |
湖畔へ下りてきたところへ乗馬の列が通りかかる |
日本では3時間歩くと聞いていましたが、歩く前のガイドさんの話では2時間ちょっとの予定。実際は、あまり時間を気にしないおばちゃん集団だからか予定よりかかったらしく、バスの運転手さんが添乗さんに何か一生懸命抗議していました。
バスの拘束時間をオーバーしたのでしょうか。このホーリーさんという運転手さんは昨日からずっと私たちを運んでくれて、ユーモア感覚のある、段差のあるところは必ずスピードを落として運転してくれる親切でサービス精神溢れる、プロ意識を感じられる人だけど、仕事の内容や時間に対して当然の権利意識は強いのでしょう。外国は大体どこもそうでしょうね。
|