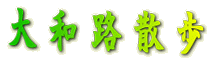
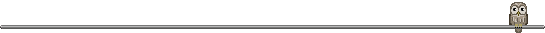
2010年2月20日(土) 晴れ だけど 雲多い <斑鳩史跡のつづき>
 |
| 伝法堂裏側 |
法隆寺東院伽藍、夢殿の北にある伝法堂(でんぽうどう、国宝)は、聖武天皇の夫人、橘古那可智(たちばなのこなかち)の住居を仏堂として移築したと言われる。例年7月24日の地蔵会(じぞうえ)の夕方短時間しか開扉されない伝法堂が2月18日から28日まで特別開帳され、3組の阿弥陀三尊像(重文)はじめたくさんの仏像を拝観させてもらった。
特別開帳だけど拝観料を別に取るということはなく、いつものとおりの200円払えば東院伽藍内は見学できた。
 |
 |
| 絵殿 |
舎利殿 |
入り口は伝法堂の南側、夢殿と向かい合っている絵殿と舎利殿がつながった建物にあって、短い廊下を渡り、伝法堂の回廊からの参拝となる。今日で開扉から3日目でも、内部から古いお堂特有のひんやりした空気が漂って、大きさいろいろ、種類もいろいろの仏像たちが並んでいた。開けられた扉3ヶ所に急拵えらしい仏像名称を書いた紙が張り出してあり、みなさん、実物と名前を交互に見比べながら貴重な体験を喜んでいるよう。
名前を書いた紙の写しはもらえないのかと聞いてみたが、何せ滅多にないことなので、聞かれる人が多いから張り出したのがやっとということだった。ここは杖使用はだめで、足の悪い人がひとりで来たらそばに立っている関係者に手を引いてもらうのだろうか。
右の地図をクリックすると別窓で大きい地図が出ます。
境内写真などは2007年はこちら、2008年はこちらでどうぞ。
 時間はたっぷりある。好きなだけうろうろするぞと西院伽藍に入った。入ってすぐ前にあるのは五重塔。左写真は奥から撮っている。入り口は写真の五重塔の裏のあたり。 時間はたっぷりある。好きなだけうろうろするぞと西院伽藍に入った。入ってすぐ前にあるのは五重塔。左写真は奥から撮っている。入り口は写真の五重塔の裏のあたり。
塔の東西南北四面は、それぞれ階段を上がって中を見られる。立体的に塑形された山を背景として塑造の群像が配された珍しい光景だ。
711年に造立されたという。東面に「唯摩詰像土」、北面に「涅槃像土」、西面に「分舎利仏土」、南面に「弥勒仏像土」が表現されているとか。
それにしても私の記憶のあやふやなことは呆れるばかり。初めて見たときの衝撃が大きかったにしても、
我ながら驚くばかりの記憶違い。
今回中を覗いてあれっと思ったのだ。こんなに小さかった? もっと5倍も10倍も一面が大きいと思い込んでいた。あれれ、あれれと信じられないまま1周した。
この頃こんなことばかり。すばらしいと感じたものはずっと大きく、あまり好きじゃないものは小さく覚えていそうだ。これも老化のひとつだろうか。どんどん話が膨らんでいくのは昔からだけど、大きさの印象まで違ってしまうのかぁ・・・
五重塔の隣の建物は金堂。前回は内部須弥壇の修理中で扉は閉じられ、中の仏像は上御堂に一時安置されてそちらで拝観した。
修理後初めて来て、本尊の釈迦三尊像は元通り安置されていたが、以前と大きく違うと感じたのは堂内の明るさ。特に仏像たちに灯かりが射している感じ。修理前は真っ暗でおそらく扉から入る光しかなかったと思う。小さい懐中電灯で仏像のお顔を照らしている人をよく見た。今回もそういう人がいたけれどひとりだけ。
熱を発さない、光の当たったところを変化させない灯かりがつけられたのじゃないだろうか。教科書にも載っている有名な古代仏。やっぱりちゃんと見えるのはうれしい。
下の地図をクリックすると拡大図が出ます。

 西院伽藍回廊の一番北の建物、大講堂が今回修理中だった。屋根だけなのか、瓦が乗っていない裸の屋根からすっぽり網のような仮家が覆っていた。右写真の梅の木の向こう側。内部の拝観はできた。 西院伽藍回廊の一番北の建物、大講堂が今回修理中だった。屋根だけなのか、瓦が乗っていない裸の屋根からすっぽり網のような仮家が覆っていた。右写真の梅の木の向こう側。内部の拝観はできた。
法隆寺は仏像もお宝も多くて、特別なのは、西院伽藍の外の大宝蔵院に常時展示されている。一番のお宝は百済観音像だろう。回廊の北面に一体だけ大きなガラスケースに入っている。横からも拝観できるようになっているのがすごい。
他にも夢違観音や玉虫厨子などなど国宝がずらっと並んで、圧倒される。法隆寺はやっぱりすごい。
滅多にお守りやおみやげの類は買わないが、しおりを2枚買った。金ぴかすぎるけど、そのうちに黒ずんでくるだろうし、五重塔も百済観音像も造られたときはきっと金ぴかや赤や緑の色鮮やかなものだっただろう。気にせず使うとしよう。
西院伽藍の建物などの写真は2007年はこちら、2008年はこちらをどうぞ。
西円堂にも行っていないし、まだゆっくり法隆寺を楽しむつもりだったけど、大宝蔵院で展示物を見ているうちに、何だか疲れて少し気分も悪くなって、急いで外に出た。ベンチに腰掛けて休憩すればいつものように元気が戻るかと思ったが、無理に全部まわることもない。次は3月に中宮寺の特別開帳に来るつもりだし、おとなしく帰ることにした。京都でも途中でちょっとしんどくなった。まだまだ体調がそれほど本調子じゃないということらしい。あせらない、あせらない。のんびりいこう。
|